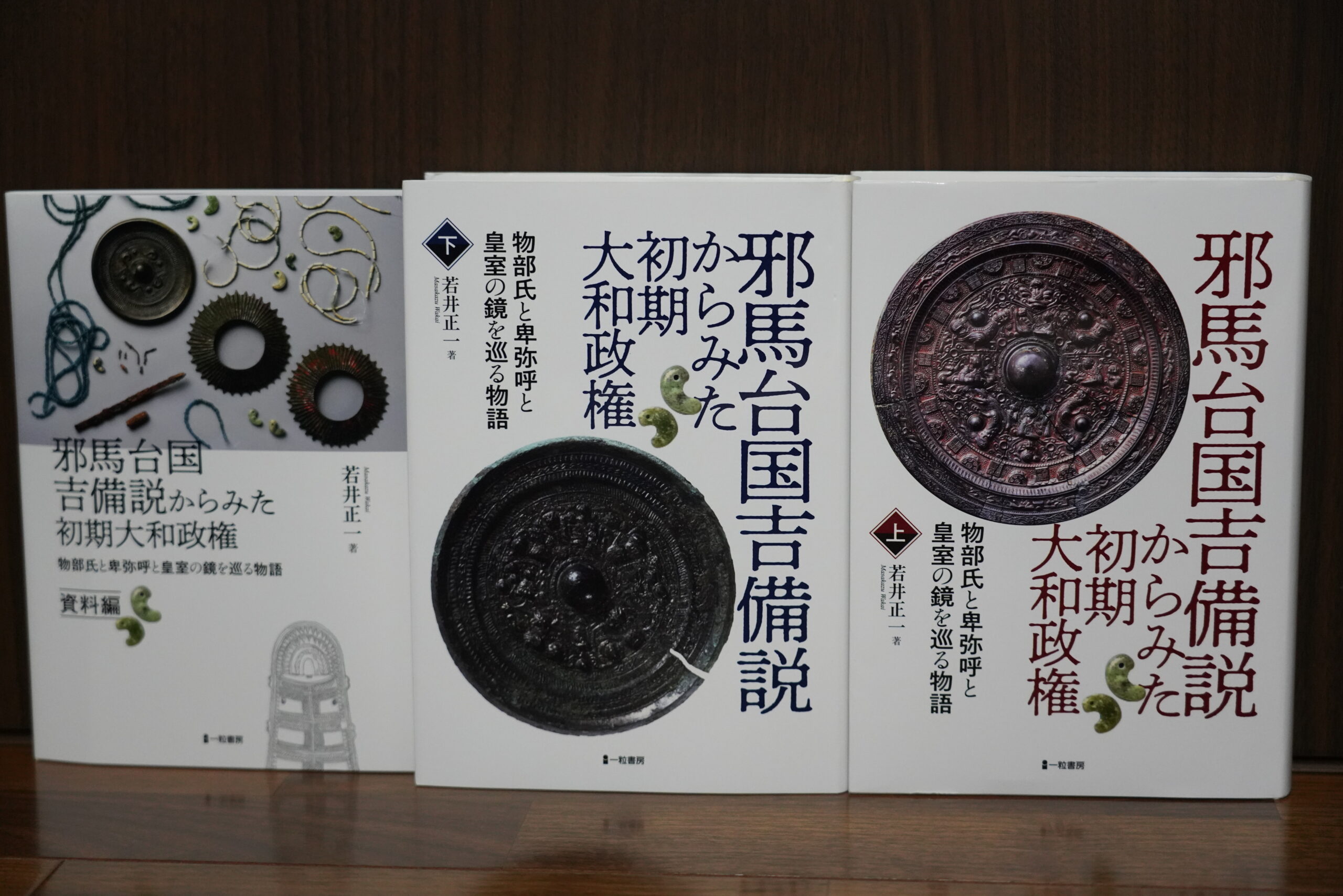『倭国の激動と任那の興亡 列島国家への軌跡』という拙著を最近上梓しました〔注1〕。紙の書籍はamazonなどにてお求めいただけます(1200円+税)。電子書籍〔Kindle版〕もあります(800円)。
本ブログではこの近著の解説および関連記事を順次アップロードしていく予定です。そこで手始めに、<はじめに>の中からいくつかのテーマを取り上げます。
この近著は三世紀後半から六世紀にかけてを対象としていますが、<はじめに>はそれから逸脱しています。これは、古代から現代に至るまでの我が国の対外戦争を俯瞰し、その帰結としての現状を概説し、我々がこれから進むべき道を考察するものです。その本旨は、古代を論ずるに当たって、自らの歴史観や思想信条を示すことにあります。よって、<はじめに>は第一章以降の内容とは異色のものとなっています。
<はじめに>(頁1~164)
第一節 歴史への畏れを失った戦後古代史学
第二節 近代日本の蹉跌と教条主義の蔓延
第三節 新羅の入寇、刀伊の入寇、そして元寇
第四節 倭寇、秀吉、そして近代日本
第五節 大東亜戦争の敗北と新たなる東亜新秩序の希求
第六節 近代の超克としての尊皇攘夷と原点への回帰
このうち本稿では、朝鮮半島南部の名称を題材とします。
〔アイキャッチ画像〕は、国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)〔以下、歴博と略す〕が展示する、「5世紀の東アジア地図」というパネルの一部です(2025年6月15日時点)。ちなみに、歴博は我が国の歴史を専門とする国立の機関であり、その権威は絶大です。
私見では、この五世紀の地図には誤りがあります。朝鮮半島の南西部に位置する、全羅北道および全羅南道の一部が百済領となっていることです。この地域が百済領になったのは、六世紀であって五世紀ではありません。これについては近著〔注1〕の第三章で詳述しました。ただし、ここで問題にしたいのは、そのことではありません。
本稿で取り上げたいのは、この展示が朝鮮半島南部を「加耶」と表記していることです。今日においては、これに限らず、他の主要な展示会にしろ、刊行物にしろ、高校教科書にしろ、「加耶」あるいは「伽耶」の表記が一般的です。「加耶(伽耶)」すなわち「かや」という訓みが歴史的な呼称であるというのです。
例えば、歴博は2022年に『加耶 古代東アジアを生きた、ある王国の歴史』という企画展を開催しました。その展示図録は、朝鮮半島南部の名称を「加耶」で統一しています。
高等学校の日本史教科書でも同様です。山川出版社の『詳説日本史』〔注2〕は、「加耶(加羅)諸国」(頁26)あるいは「加耶諸国」(頁33)と記述することで、加耶(かや)が本来の名称であると高校生に教えています。
教科書に限りません。今日出版されている古代史の書籍の殆どすべては、「加耶」あるいは「伽耶」と記しています。これまた「かや」なのです。
ところが、古代の史料に当たると別の様相が見えてきます。414年の好太王碑文にしろ、五世紀末~六世紀初頭に撰述の中国の正史『宋書』倭国伝にしろ、720年に成立の本邦最古の正史『日本書紀』にしろ、その表記は「加羅」(から)です。朝鮮の史料にも「から」はあります。十三世紀撰述の史書『三国遺事』に、十一世紀の記録の抄録が掲載されており、そこに「駕洛」(から)があります。すなわち、内外の史料によれば、「から」が本来の訓みなのです。
それに対して、「加耶(伽耶)」(かや)が史料上初めて登場するのは、1145年に成立した朝鮮最古の正史『三国史記』です。
「から」であろうと「かや」であろうと、どちらでも良いではないかと思われるかもしれません。些細な違いに過ぎない、と。しかし、そんなことはありません。
なぜなら、私見では、「から」の語源は日本語であるからです。これについて詳しくは近著〔注1〕で説明しました。
ここでは、次のことを指摘するに留めます。平安時代の美術において、我が国の風物を題材とした大和絵(やまとえ)に対して、中国の故事や風景を描いた作品を唐絵(からえ)と言います〔注2、頁67〕。あるいは、鎌倉時代後期から室町時代にかけて、交易により大量の中国製品が我が国にもたらされ、貴人の間で大流行しました。これを唐物(からもの)と言います。私見では、この「唐」(から)は「加羅」(から)と同根です。「加羅」は朝鮮半島南部のこと、「唐」は中国のことです。にもかかわらず、我々はどちらも「から」と呼称します。それは何故なのでしょうか?それは、日本語の古語「から」とは元来は海外の土地を意味する普通名詞であるから、というのが私の考えです。
戦後にあっても昭和の時代までは史学者は「加羅」と表記していました。ところが、平成の世に入るや間もなく、彼らは「加耶(伽耶)」に乗り換え、その普及に勤しみ始めました。1989年7月に「東アジアの古代文化を考える会」が開催した『伽耶はなぜほろんだか』というシンポジウムにその端緒が見られます〔注3〕。
古代史アカデミアは、「から」(加羅)ではなくて「かや」(加耶)が学問的に妥当であるという根拠を未だかつて示していません。この学術集団は、「から」から「かや」に唐突かつ一斉に変更した経緯を公に説明していません。
史学者たちの曲学阿世が学問としての古代史を貶めているのです。我々が採るべきは歴史に則した用語であるべきです。
〔注1〕若井正一 2025『倭国の激動と任那の興亡 列島国家への軌跡』(一粒書房)
〔注2〕山川出版社『詳説日本史』〔日本史探究〕令和4年文部科学省検定済・令和5年発行
〔注3〕鈴木靖民ら八名(著) 1998『増補改訂版 伽耶はなぜほろんだか』(大和書房)
2025年10月20日 投稿