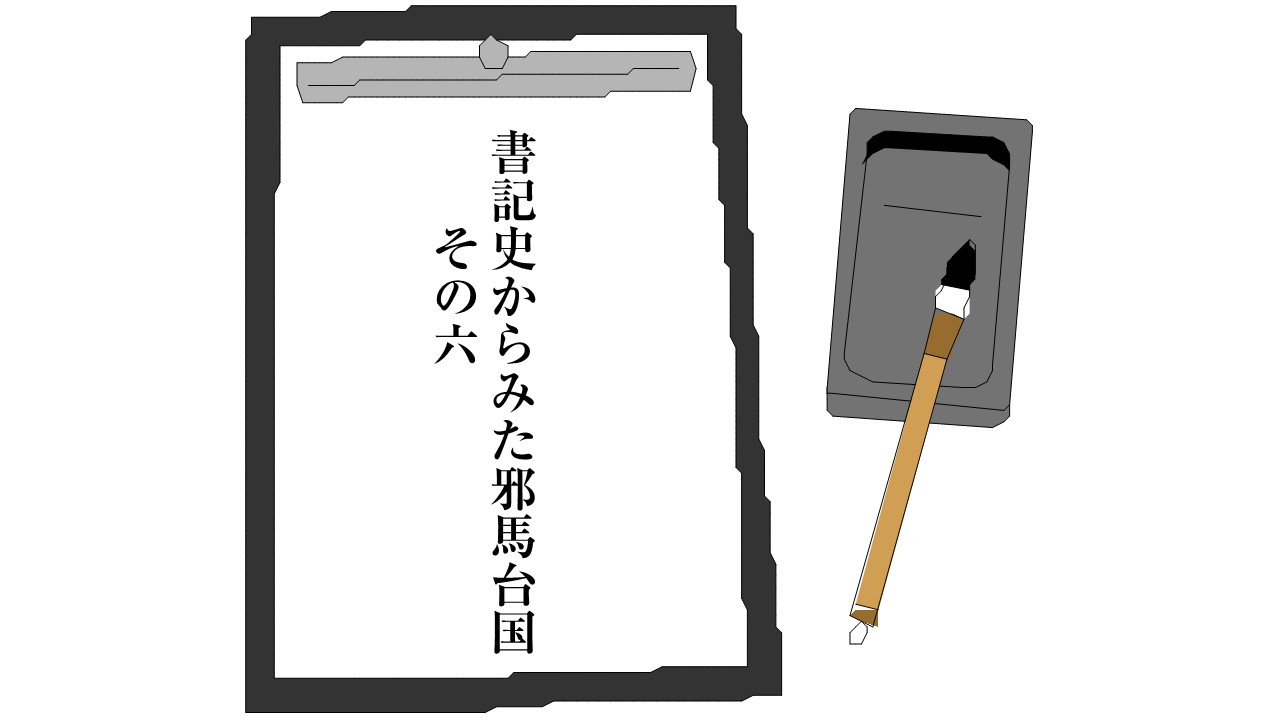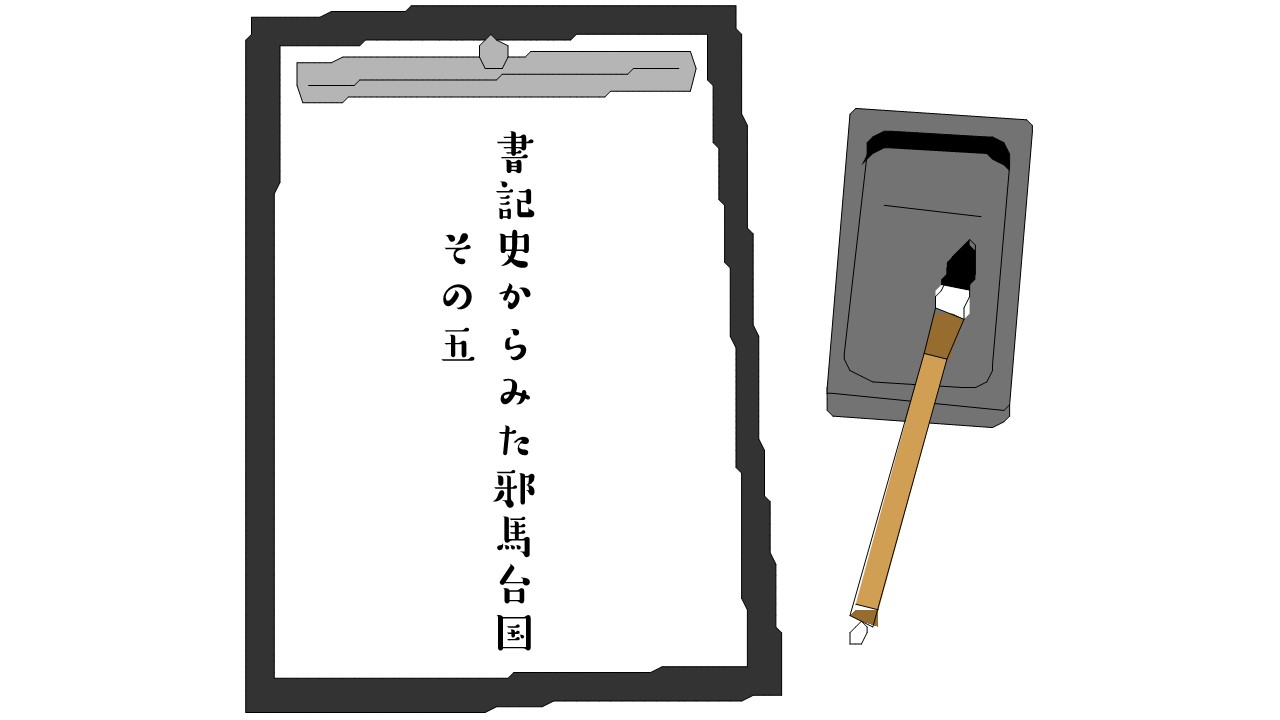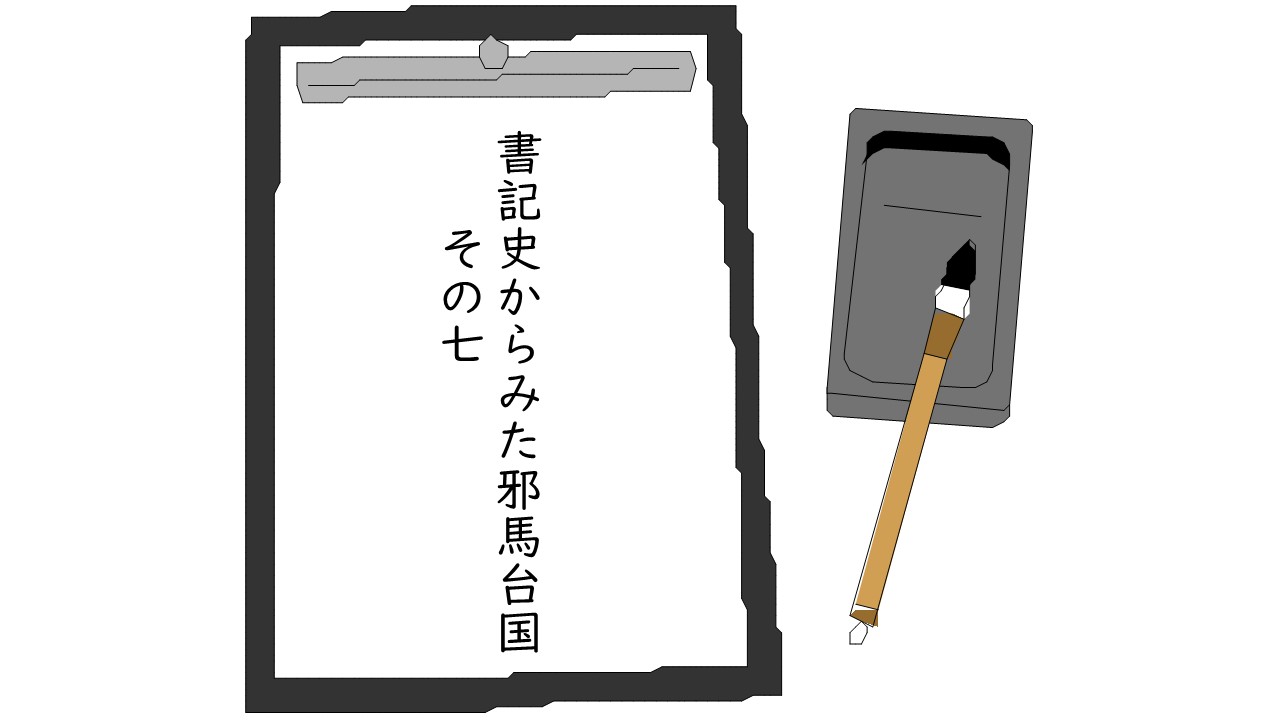以下は、2021年3月15日に投稿した記事です。
書記史からみた邪馬台国 その六
本稿は、「その一」、「その二」、「その三」、「その四」、「その五」に続くものである。
我が国の書記史に関して、ここ数年の間に考古学は従来の常識を覆した。それにより認識を新たにしたのは、時間的な深まりと空間的な広がりである。
書記の時間的な深まりについては既に解説している。
繰り返すと、中国における板石硯は前漢中期に現れた。紀元前150年~紀元前50年である。一方、我が国における板石硯の製作は須玖Ⅰ式新相に始まった。となると、その製作開始は紀元前2世紀中頃~末となる。つまり、板石硯の出現は中国と我が国とはほぼ同時期である。
このことは、倭人すなわち我々の祖先は、紀元前2世紀代には漢字文化圏に入っていたことを意味する。倭において文書の読み書きを専門とする人々を、ここでは史(ふひと)と呼ぶ。板石硯を使用していたのはこの人々である。北部九州の各国は独自に史を抱えることで中国王朝と文書外交を展開していたのである。
ところで、前漢の武帝が朝鮮半島に楽浪郡を設置したのは紀元前108年である。楽浪郡の場所は現在の平壌(ピョンヤン)とされる。紀元前1世紀には、楽浪郡と北部九州との間に人の行き来があった。この時期の北部九州に楽浪系土器が出土するからだ。その往来の中継地点が勒島遺跡(ヌクド遺跡)である。これは朝鮮半島南岸部の小島にある。この交流は「勒島貿易」と呼ばれる〔注1〕〔注2〕。ちなみに勒島遺跡からは北部九州の弥生土器が多数出土している。北部九州から楽浪郡へ向かう倭人が残したものであろう。
紀元後1世紀になると勒島遺跡は衰退していった。それに代わって台頭したのが半島南岸部の金海(大韓民国慶尚南道金海市)である。楽浪郡、金海、原の辻遺跡(壱岐)、三雲遺跡(糸島)を結ぶ交通路は「原の辻=三雲貿易」と呼ばれる〔注2〕。
原の辻=三雲貿易では、倭の史と楽浪郡の官人の間で文書が取り交わされていたと思われる。そのことを窺わせるのが、書記史見直しのきっかけとなった発見である。2016年3月2日に新聞各紙によりリリースされた、糸島市教育委員会の衝撃的発表のことである。その内容とは、同市の三雲・井原遺跡の番上地区で、弥生時代後期(1~2世紀)の硯の破片が出土したというものだ〔注3〕。これは古の伊都国の中心地である。
この発見で注目されるのは、その番上地区は楽浪系土器が集中する場所であることだ〔注3〕。このことは、まさにその場で伊都国の史が文書を作成し、それを楽浪郡からの使者に渡していたことを思わせる。
次に、書記の空間的な広がりを見てみよう。
板石硯は北部九州だけに分布するのではない。それは、弥生時代中期後半以降、西日本の各地に広がった〔注4〕。そのうち世の耳目を集めたのが、島根県松江市の田和山遺跡から出土したものである。そこの弥生時代中期後半の遺構に複数個の板石硯が見いだされた。2020年、そのうちの一つに墨書き文字が認められると発表され〔注5〕、「日本最古の文字」として大いに話題になった。発見者である久住猛雄はそれを「子戊」と解読している〔注6〕。それに対して柳田康雄は「壬戌」の可能性を指摘している〔注4〕。いずれにせよ、板石硯に文字が書かれていたことは、硯の用途が書記であったことを確かにする。
板石硯は日本列島でどのように広がっていたのだろうか?久住猛雄によれば〔注5〕、北部九州の玄界灘沿岸と朝倉地方では弥生時代中期後半に、日本海沿岸では後期初頭には伝播していた。ただし、前述の松江市田和山遺跡では中期後半である。瀬戸内海沿岸~近畿地方では概ね後期初頭である。東海地方では終末期(庄内式併行期)であるという。
これは一体何を意味するのであろうか?次回に考えてみよう。
つづく
〔注1〕白井克也 2001「勒島貿易と原の辻貿易 粘土帯土器・三韓土器・楽浪土器からみた弥生時代の交易」『弥生時代の交易 モノの動きとその担い手』第49回埋蔵文化財研究集会:埋蔵文化財研究会
〔注2〕久住猛雄 2007「『博多湾貿易』の成立と解体 古墳時代初頭前後の対外交易機構」『考古学研究』第53巻第4号(通巻212号):考古学研究会
〔注3〕武末純一・平尾和久 2016「<速報>三雲・井原遺跡番上地区出土の石硯」『古文化談叢』第76集:九州古文化研究会
〔注4〕柳田康雄 2020「倭国における方形板石硯と研石の出現年代と製作技術」『纏向学研究』第8号:桜井市纏向学研究センター
〔注5〕久住猛雄 2020「近畿地方以東における『板石硯』の伝播と展開」第34回考古学研究会東海例会『荒尾南遺跡を読み解く~集落・墓・生業~』(2020年2月1日・2日 大垣市スイトピアセンター)
〔注6〕久住猛雄 2020「松江市田和山遺跡出土『文字』板石硯の発見と提起する諸問題」『古代文化』第72巻第1号:古代学協会
以上、2021年3月15日投稿記事
以下は、2025年9月14日の追記である。
田和山遺跡出土板石硯の「墨書き文字」は、後に、現代の油性マーカーによる書き入れであることが明らかになった。それは、弥生人の手による文字ではなくて、発掘後の遺物整理中に意図せず記されたものとの見方が強まった〔朝日新聞 2022年9月9日記事〕。これを受けて久住猛雄は、田和山遺跡石製品の表面に弥生時代の墨書き文字があるという主張を公に誤りであると認めて撤回した〔注7〕〔注8〕。要するに、それは「日本最古の文字」ではなかったわけだ。
〔注7〕久住猛雄 2023「弥生時代の板石硯」宮本一夫(編)『季刊考古学・別冊43 九州考古学の最前線1 縄文~古墳編』雄山閣
〔注8〕久住猛雄 2024「高地性集落における北部九州系土器と『板石硯』の出土とその意義 田和山遺跡と用木山遺跡」『「高地性集落」論のいま 半世紀ぶりの研究プロジェクトの成果と課題』二〇二〇~二〇二三年度科学研究費助成事業(研究代表 森岡秀人)〔シンポジウム開催:令和6年3月2日 京都〕:発表要旨集
2025年9月14日 投稿