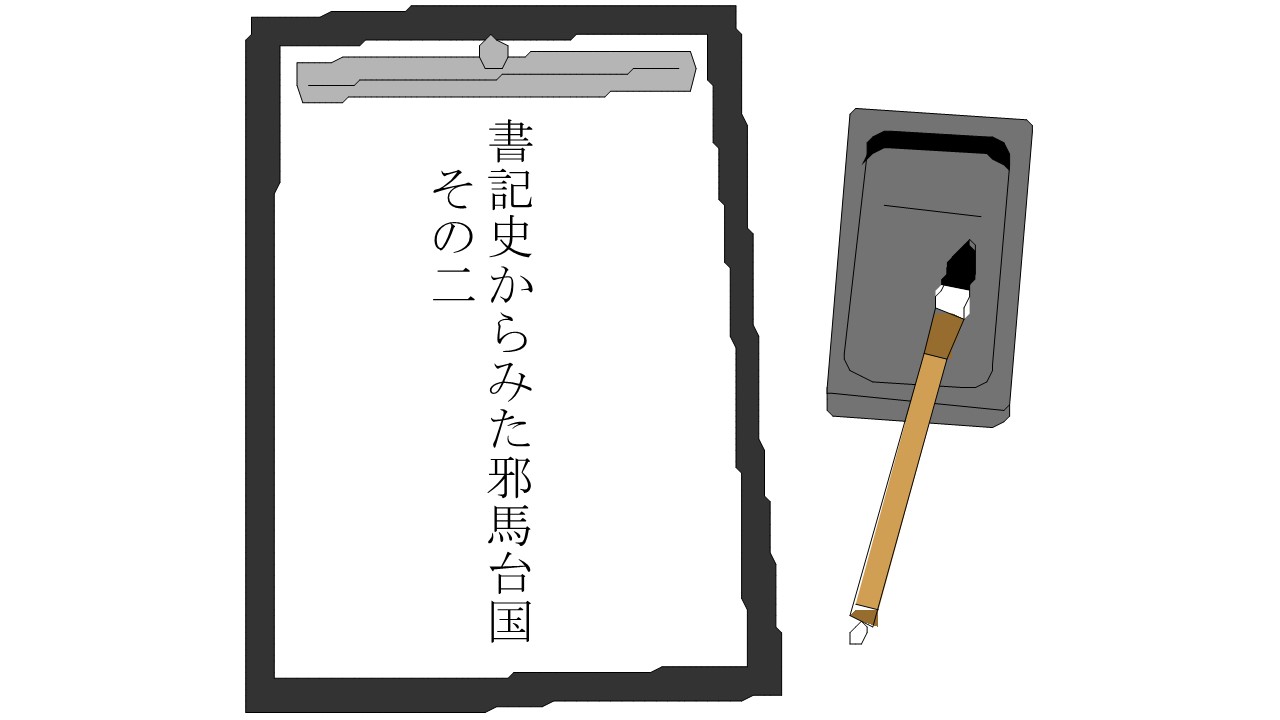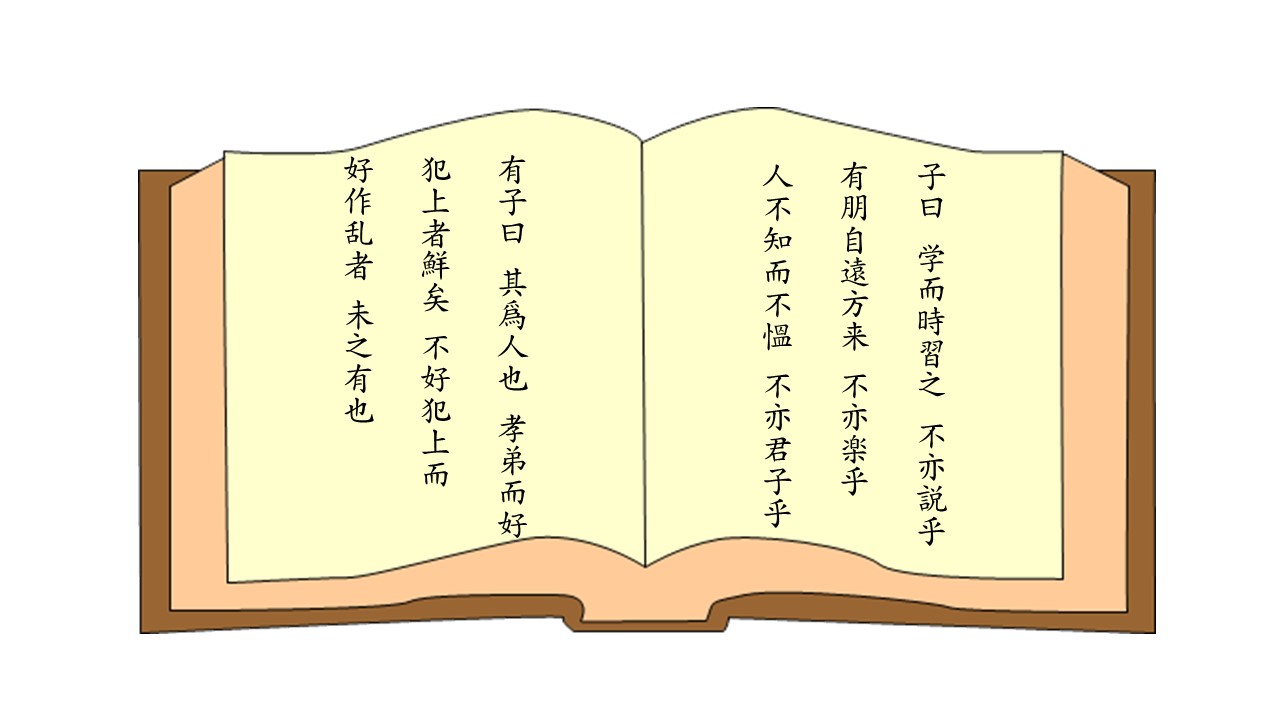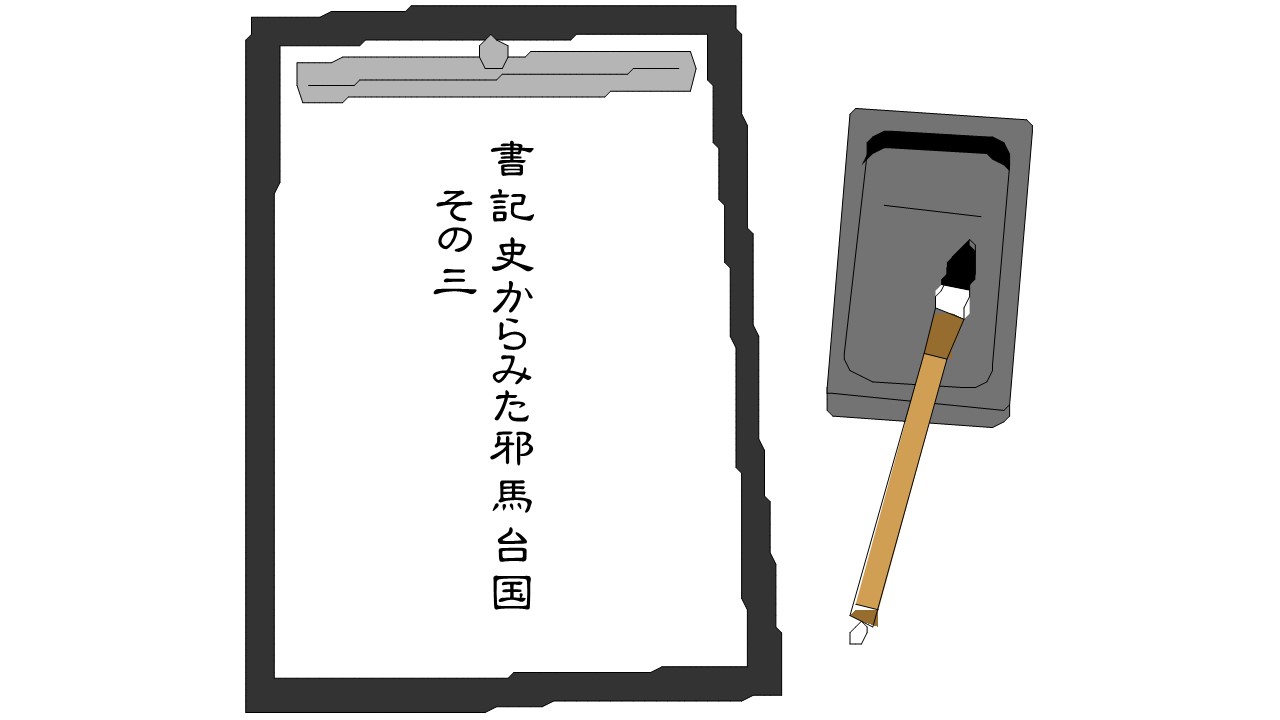以下は、2020年12月5日に投稿した記事です。
書記史からみた邪馬台国 その二
先の投稿で、弥生時代に石製の硯(板石硯)が製作されていたとする報告を取り上げた。そして、これは戦後最大級の考古学上の発見であると述べた。なぜなら、それは従来の常識や学説に再考を迫るものであるからだ。
本稿で取り上げたいのは弥生時代中期の年代論である。
北部九州の弥生時代中期は、土器型式として、城ノ越式、須玖Ⅰ式、須玖Ⅱ式の順に変遷する。
国立歴史民俗博物館(歴博)の研究グループは、弥生時代の始まりを紀元前10世紀後半とし、城ノ越式の始まりを紀元前4世紀中頃とし、須玖Ⅰ式の始まりを紀元前300年頃とし、須玖Ⅱ式の始まりを紀元前3世紀末とする〔注1〕〔注2〕。
この歴博グループの年代観に疑問を呈するのが九州の考古学者である。
福岡大学の武末純一は、城ノ越式の始まりを紀元前300年頃とし、須玖Ⅰ式の始まりを紀元前2世紀前半とし、須玖Ⅱ式の始まりを紀元前2世紀後半とする〔注3〕。
國學院大學の柳田康雄は、城ノ越式の始まりを紀元前3世紀末とし、須玖Ⅰ式の始まりを紀元前2世紀前半とし、須玖Ⅱ式の始まりを紀元前1世紀初頭とする〔注4〕。
福岡市の久住猛雄は、「弥生時代早期開始は古くて紀元前800年で紀元前8世紀のうち、中期初頭は紀元前3世紀前半頃、須玖Ⅱ式開始は紀元前2世紀末、終末期(庄内式)初頭は180年頃、『布留0式』(古墳時代初頭)の上限は250年前後と考えている」〔注5〕と述べる。
このように久住は古墳時代(布留0式)の開始を紀元後250年頃とする。この年代観は歴博グループ〔注2〕と同じである。ところが、弥生時代については、両者は一致しない。
久住によれば、弥生時代早期の開始が紀元前8世紀であり、城ノ越式の開始が紀元前3世紀前半頃であり、須玖Ⅱ式の開始が紀元前2世紀末であるという〔注5〕。要するに、久住の見解は、弥生時代早期については150年~200年、弥生時代中期については50年~100年、歴博グループより新しい。
ただし、弥生時代終末期(庄内式)の始まりについては、歴博グループは2世紀後葉とし〔注2〕、久住は180年頃とすることから〔注5〕、両者に大きな違いはない。私は、庄内式および布留式の開始年代について、久住猛雄〔注5〕〔注6〕や若林邦彦〔注7〕〔注8〕や森岡秀人〔注9〕らと同様な年代観に立って、邪馬台国吉備説を説いた〔注10〕。
本稿では、話を弥生時代中期に絞ろう。
先述したように、歴博グループは、城ノ越式の始まりを紀元前4世紀中頃とし、須玖Ⅰ式の始まりを紀元前300年頃とし、須玖Ⅱ式の始まりを紀元前3世紀末とする。本稿では、これを「歴博年代」と呼ぶ。
それに対して、九州の考古学はどうであろうか?武末純一、柳田康雄、久住猛雄のいずれの年代観も歴博年代より新しい。とはいえ、三名の年代観が一致しているわけではない。そこで本稿では、それらを総合して、城ノ越式の始まりを紀元前3世紀初頭とし、須玖Ⅰ式の始まりを紀元前2世紀前半とし、須玖Ⅱ式の始まりを紀元前2世紀末とし、これを以て「九州考古学年代」と呼ぶ。
見比べてみれば分かるように、歴博年代は九州考古学年代に比して、おおよそ100年古い。
さて、ここからが本稿の佳境である。
我が国における板石硯の製作は須玖Ⅰ式新相に始まった〔注4〕〔注11〕。となると、その製作開始は、歴博年代では紀元前3世紀中頃~末となり、九州考古学年代では紀元前2世紀中頃~末となる。
ところで、中国における板石硯は前漢中期に現れたとされる〔注12〕。前漢の時代は、紀元前202年~紀元後8年である。となると、中国でのその登場は紀元前150年~紀元前50年となる。
とすると、歴博年代によれば、板石硯の出現は我が国の方が中国より早いことになる。一方、九州考古学年代によれば、その出現は中国と我が国とはほぼ同時期となる。
文字の使用は中国大陸にはじまり、我が国に普及した。硯は筆記用具である。従って、硯の製作に関して、我が国が中国に先行することはあり得ない。
柳田康雄は、歴博の年代観では「中国より約100年早く北部九州で方形板石硯や方形研石が出現することになり」、その年代観は誤りであると主張した〔注4〕。確かに柳田の言う通りである。板石硯の考古学の見地から、弥生時代中期に関する歴博年代には無理がある。それに関して九州考古学年代の方が妥当である。
つづく
〔注1〕藤尾慎一郎 2009「較正年代を用いた弥生集落論」『国立歴史民俗博物館研究報告』第149集:国立歴史民俗博物館
〔注2〕小林謙一・藤尾慎一郎・松木武彦 2020「先史時代(縄文・弥生・古墳)の年代と時代区分」中塚武・若林邦彦・樋上昇(編)『気候変動から読みなおす日本史3 先史・古代の気候と社会変化』臨川書店
〔注3〕武末純一 2020「弥生時代日韓交渉を巡るいくつかの問題 総論に代えて」『新・日韓交渉の考古学 弥生時代(最終報告書 論考編)』「新・日韓交渉の考古学 弥生時代」研究会
〔注4〕柳田康雄 2020「倭国における方形板石硯と研石の出現年代と製作技術」『纏向学研究』第8号:桜井市纏向学研究センター
〔注5〕久住猛雄 2016「日本列島の弥生時代と日韓交渉 ~北部九州・福岡平野周辺を中心に~」釜山広域市福泉博物館『国際学術シンポジウム 原始・古代の韓日交流』(2016年11月11日)配布資料
〔注6〕久住猛雄 2017「発表 北部九州からみた楯築弥生墳丘墓の時代の考古編年の併行関係と実年代」ならびに「討論」考古学研究会岡山例会委員会(編)『考古学研究会例会シンポジウム記録11 楯築墓成立の意義』(岡山例会第20回シンポジウム 2015年10月31日 岡山)考古学研究会
〔注7〕若林邦彦 2018「近畿地方弥生時代諸土器様式の暦年代 石川県八日市地方遺跡の研究成果との対比」『同志社大学考古学シリーズⅫ 実証の考古学 松藤和人先生退職記念論文集』同志社大学考古学研究室
〔注8〕若林邦彦 2020「気候変動と古代国家形成・拡大期の地域社会構造変化の相関 降水量変動と遺跡動態から」中塚武・若林邦彦・樋上昇(編)『気候変動から読みなおす日本史3 先史・古代の気候と社会変化』臨川書店
〔注9〕森岡秀人 2018「倭国形成過程と庄内式期開始年代論争をめぐる鼎談2017 福永伸哉VS岸本直人VS森岡秀人 断章」『古墳出現期土器研究』第5号:古墳出現期土器研究会
〔注10〕若井正一 2019『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権 物部氏と卑弥呼と皇室の鏡を巡る物語』一粒書房
〔注11〕久住猛雄 2020「近畿地方以東における『板石硯』の伝播と展開」第34回考古学研究会東海例会『荒尾南遺跡を読み解く~集落・墓・生業~』(2020年2月1日・2日 大垣市スイトピアセンター)配付資料
〔注12〕吉田惠治 2018『ものが語る歴史38 文房具が語る古代東アジア』同成社
以上、2020年12月5日投稿記事
以下は2025年9月13日の追記です。
2020年12月5日の投稿では、弥生時代中期の始まりに関して、歴博年代は無理があるとして九州考古学年代に軍配を上げた。しかし、その後の検討の結果、考えを改めた。若林邦彦の主張(上記の〔注7〕)を読み返して、そこに説得力を感じたからである。奈良県中西遺跡や石川県八日市地方遺跡(石川県ようかいちじかた遺跡)から出土した資料に、年輪年代測定、炭素14年代測定、酸素同位体比年輪年代分析を施した研究が次々と発表された。それらの結果を総合した若林は、「これにより想定できる近畿地方における弥生時代~古墳時代前期の歴年代観は、弥生前期が紀元前四世紀初頭以前、弥生中期が紀元前四世紀中葉ー紀元前一世紀、弥生後期が紀元一世紀ー二世紀、古墳初頭が紀元二世紀後葉~三世紀前葉、古墳前期が紀元三世紀後中葉以後といえよう」〔注7、頁128〕と結論した。こうして、「弥生時代は早期・前期・中期・後期の四つに大きく分かれ、それぞれ、紀元前10世紀後半、紀元前780年、紀元前350年、紀元後50年頃に始まり、箸墓古墳の出現をもって古墳時代とする場合は、紀元後250年前後に弥生時代は終わる。したがって存続期間は、順に早期170年、前期430年、中期400年、後期200年の計1200年となる」〔注13〕という暦年代観が有力となった。
この年代観は今日にあって定説になりつつある〔注14〕。最近では、国立科学博物館が開催した特別展「古代DNA 日本人のきた道」においても、この年代観が採用されている〔注15〕。まもなく上梓予定(2025年10月)の拙著『倭国の激動と任那の興亡 列島国家への軌跡』(一粒書房)においても、弥生時代中期の始まりを紀元前350年頃とする年代観を採用した。
〔注13〕藤尾慎一郎 2020「第三節 弥生時代の年代 第二章 先史時代(縄文・弥生・古墳)の年代と時代区分」中塚武・若林邦彦・樋上昇(編)『気候変動から読みなおす日本史3 先史・古代の気候と社会変化』臨川書店
〔注14〕大阪府立弥生文化博物館令和5年度冬期特別展(2024年)『紀元一世紀の社会変革 弥生後期のはじまりをさぐる』図録
〔注15〕特別展(2025年)『古代DNA 日本人のきた道』図録
2025年9月13日 投稿