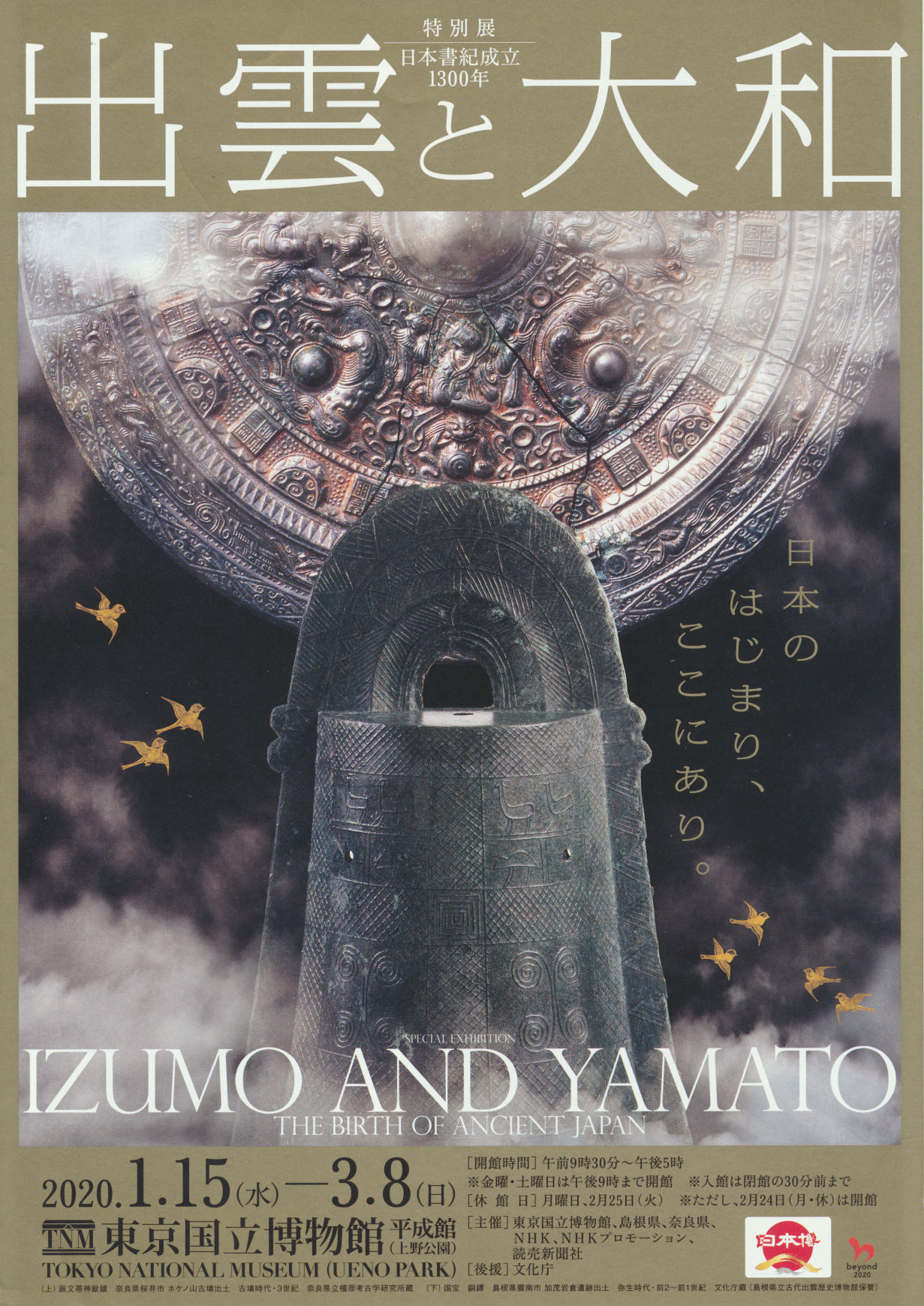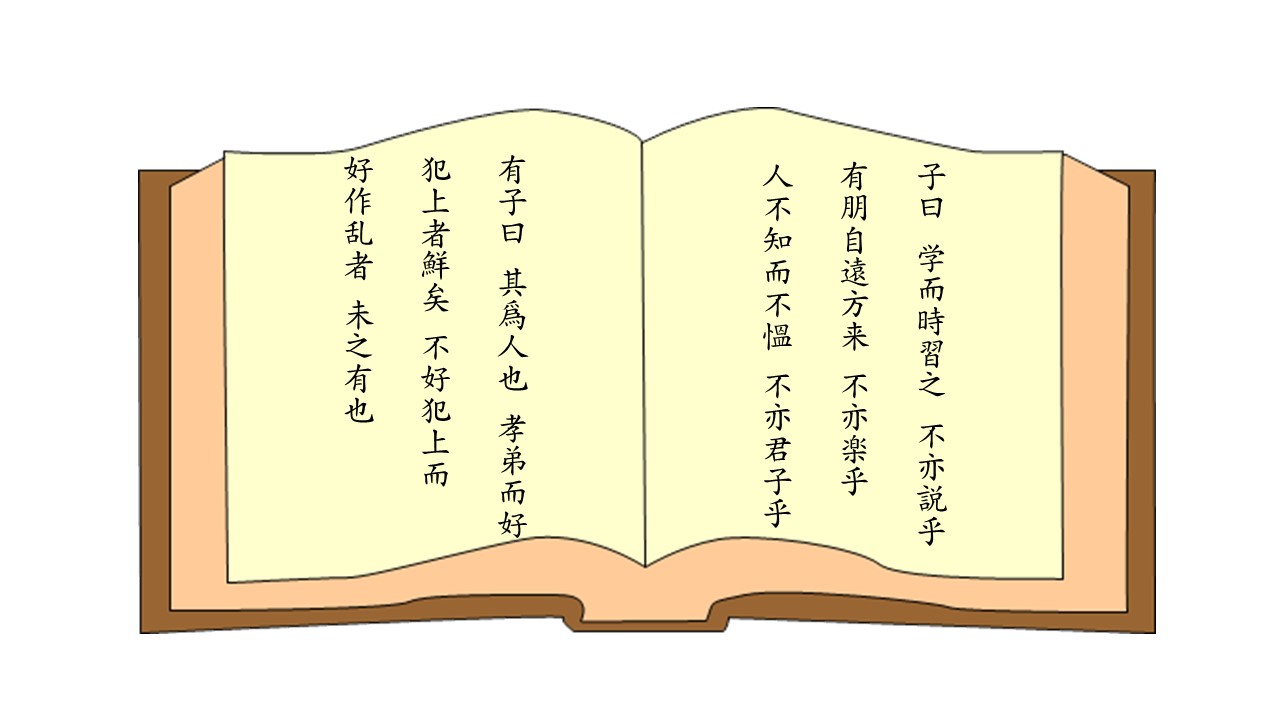以下は、2020年3月15日に投稿した記事です。
邪馬台国はヤマト国であるが、大和国ではない
『日本書紀』は養老四年五月に奏上された、我が国の公的な史書である。養老四年は西暦にすると720年である。従って、今年2020年は日本書紀成立1300年に当たる。それを記念して、令和2年1月15日から同年3月8日まで、東京・上野の東京国立博物館で特別展「出雲と大和」が開催された(アイキャッチ画像)。
私は丁度この期間中に或る会合に出席するため上京する予定があり、その機会を利用して博物館を訪れるつもりであった。ところが、その会合が世を覆う自粛の風潮のあおりを受けて急遽中止となってしまった。そのため、誠に残念なことに、件の特別展を観覧できなかった。そこで、せめてものという思いで、その図録をインターネットで購入した。
そこには、日本古代史を専門とする、奈良大学・大阪大学名誉教授の東野治之氏が、「ヤマトから日本へ―古代国家の成立」と題する論攷を寄稿している。その冒頭に次のような一節がある。
「奈良盆地とその周辺部はヤマトと呼ばれ、古代国家が成長し、律令国家として完成したところである。その歴史が現在につながることは、『日本』という国の名称がこの時期に始まることや、明治初頭まで、実態はともかく養老律令が現行法であったことに、よく表われている。しかし、その歴史の舞台となったヤマトに、広狭複数の意味があることは、案外気づかれていないのではないだろうか。ヤマトはもともと、王権の中心があった奈良盆地南東部、現在の桜井市に属する小さな地域を指す地名だった。今も大和神社という古い社があるあたりである。王権の支配地域が広がるにつれ、その中心だったヤマトの地名は、しだいに奈良盆地全体に及ぶようになる。さらにその支配が、関東から九州にまで広がったとき、ヤマトは国の名となったのである。ヤマト朝廷とかヤマト王権という用語も、それを踏まえたものにほかならない。」〔注1〕。
ここでいう「現在の桜井市に属する小さな地域」とは、具体的には、磯城(しき)地方の内の小地域を指す。明治29年に、奈良県の三つの郡、すなわち式上郡(しきじょうぐん)、式下郡(しきげぐん)、十市郡(といちぐん)が合併して磯城郡が誕生した。その後、この磯城郡から独立して生まれた市の一つが、現在の桜井市である。三世紀の大和政権の本拠地である纏向遺跡(まきむくいせき)は、この桜井市に所在する。

<写真:JR巻向駅>
古代史学者の直木孝次郎は、磯城・十市郡を中心とする一帯が、かつてはヤマトと呼ばれていたと唱えた〔注2〕。これに従えば、現在の桜井市一帯の地名はかつてヤマトであったことになる。
その上で、直木は、「このように〝やまと〟の語は、少なくとも広狭三つの意味を持っている。いまその意味を広いほうから述べたが、歴史的な発展の段階がそれとは逆であることは、いうまでもあるまい。もっとも狭義のやまと地方―大和国の一部―に成立した政権が、奈良盆地全体を勢力下におさめ、これを基盤として日本全体に支配をのばしていったために、やまとの語が次第に広い意味に用いられるようになったのであろう。これは学会の常識であって、いまさらこの問題に詳論を加える必要はないのであるが、(以下略)」〔注2〕と説いた。
先述した東野氏による論考はこの「学会の常識」を踏襲するものである。その内容は次のように要約される。ヤマトとは元々は大和政権の本拠地の地名であった。やがて大和政権は奈良盆地全体へ勢力圏を広げ、遂に日本列島全体を手中に収めるに至った。それに伴い、奈良盆地の名称が大和国(ヤマトの国)となり、日本列島全体の名称が倭国(ヤマトの国)となった。以上が、直木・東野両氏の主張である。以下、これを直木説と呼ぶ。
この直木説は、邪馬台国所在地論に大きな影響を及ぼす。というのも、邪馬台国は今でこそヤマタイ国と呼ばれるが、江戸時代まではヤマト国と読まれていたからだ。そして現在でも、邪馬台国の本来の訓みはヤマト国というのが定説である。
となると、邪馬台国とは大和国であり、よって邪馬台国の所在地は奈良盆地である。こういう結論に否が応でも導かれてしまう。なぜか言及されることは少ないが、実を言うと、これこそが邪馬台国畿内(大和)説の強力な論拠となっている。
例えば古代文学者の三浦佑之の言を借りれば、「邪馬台国の所在地については、九州か大和か、いまだに決着がつかず素人が口をはさむのは憚られるが、邪馬台をヤマタイと訓むのは間違っているということだけは主張しておきたい。音読される文字なのだから、いずれの漢字も一音で訓むべきで、とすれば、ヤマトと訓むのが妥当である。そこに最近の考古学の成果を重ねれば、邪馬台国は、三輪山麓あるいはその近辺の、ヤマトと呼ばれる地にあったとするのがもっとも自然な理解だろう。」〔注3〕というわけだ。
私はこれまで繰り返し、邪馬台国=ヤマト国=大和国という図式は間違いであると主張してきた〔注4〕〔注5〕〔注6〕。そして近著で、私説の総まとめを公とした〔注7〕。
私説の要旨は次の通りである。
「学会の常識」である直木説とは、奈良県の磯城地域の古名に過ぎなかったヤマトが、大和政権の伸張に伴ってその適用範囲が拡大され、遂には国家の名称になったというものである。しかし、この説は大間違いである。
元来のヤマトは、直木説が考えるような固有名詞ではない。それは、中心・中核を意味する普通名詞である。だから、国家を念頭に置いた場合、ヤマトとは首都の謂いである。確かに、邪馬台国はヤマト国である。しかしそれは、単に、邪馬台国は首都であると言っているに過ぎない。魏志倭人伝によれば、卑弥呼の時代、「倭国」と「狗奴国」とは戦争状態にあった。つまり三世紀前半は、日本列島が統一される前夜であった。その時代の日本列島では、二つの政治勢力圏が対峙していた。言い換えれば、首都としてのヤマト国は二つあった。吉備と大和である。魏志倭人伝が記す邪馬台国とは、後者のヤマト国ではない。それは前者のヤマト国である。つまり、邪馬台国とは吉備であり、狗奴国の都が大和(奈良盆地東南部)である。三世紀後半に大和政権が吉備王権を倒したことにより我が国は統一へ向かい、その結果、首都としてのヤマト国は一つになった。それが大和国である。以上より、邪馬台国=ヤマト国≠大和国であり、邪馬台国=ヤマト国=吉備国である。
注:
〔注1〕東野治之 2020「ヤマトから日本へ―古代国家の成立」東京国立博物館・島根県・奈良県(企画・編集)『日本書紀成立1300年特別展 出雲と大和』図録
〔注2〕直木孝次郎 1970「〝やまと〟の範囲について 奈良盆地の一部としての」橿原考古学研究所(編)『日本古文化論攷』吉川弘文館
〔注3〕三浦佑之 2007『古事記を旅する』文藝春秋、248頁
〔注4〕若井正一 2004『ヤマトの誕生 第一巻』文芸社
〔注5〕若井正一 2009『吉備の邪馬台国と大和の狗奴国』歴研
〔注6〕若井正一 2013「邪馬台国吉備説」『卑弥呼は近江か出雲か吉備か』テレビせとうち
〔注7〕若井正一 2019「第十章 ヤマトは国のまほろばであり、魏志倭人伝の邪馬台国はその一つである」『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権』一粒書房
2020年3月15日投稿
以上、2020年3月15日投稿記事
2025年9月7日 投稿