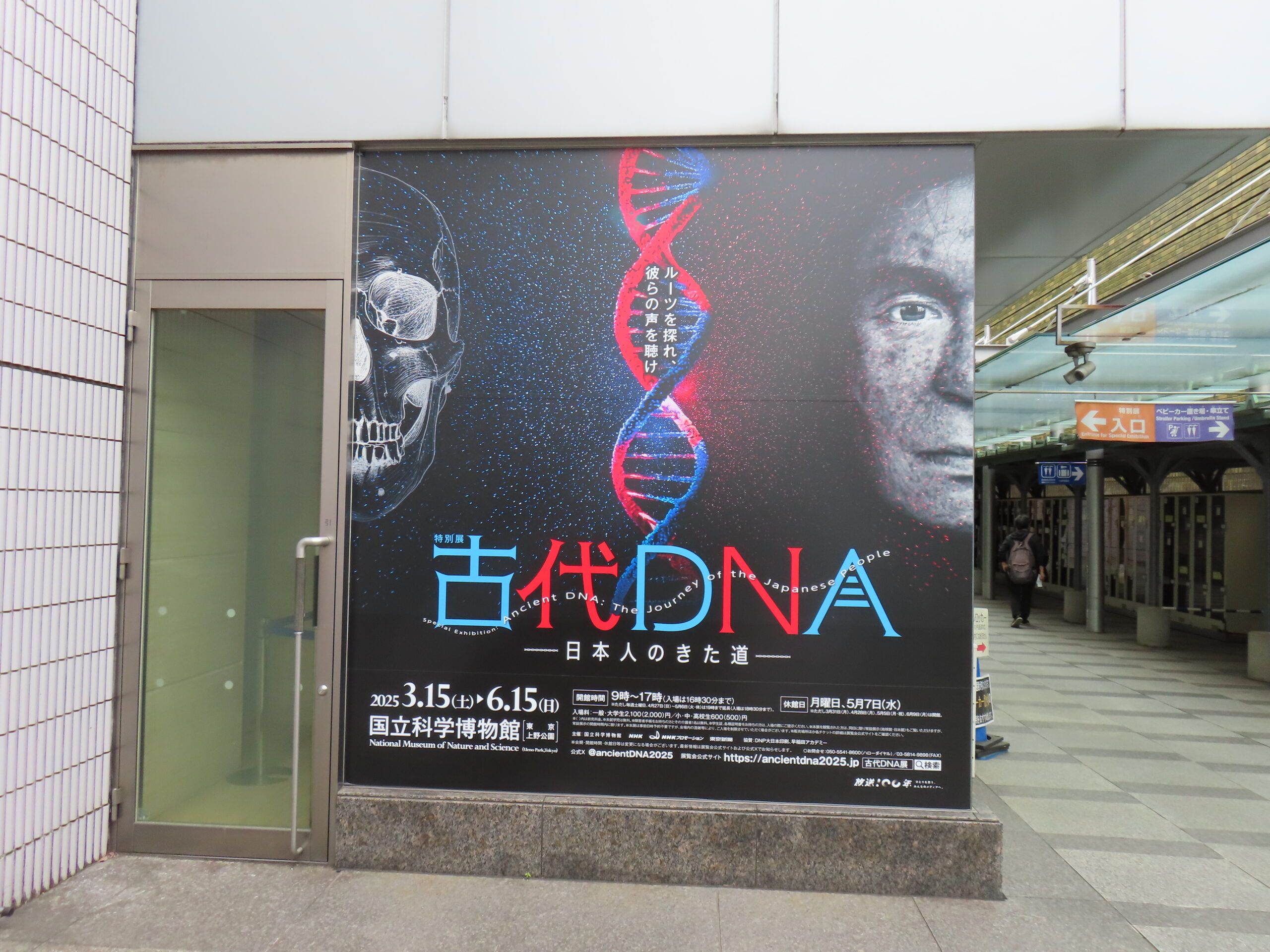以下は、2021年3月28日に投稿した記事です。
令和二年の夏にGoToトラベルキャンペーンを利用して岐阜、滋賀、京都を旅した。その旅行記を数回に分けて投稿しようと思う。本稿はその初回である。そもそも古代をテーマとする私がなぜこの地域に関心を寄せるのか?まずその趣旨を説明したい。いわばこのシリーズの総論である。
邪馬台国に関わる議論となると、その対象時期は、弥生時代後期、庄内式期、古墳時代前期前半である。西暦で言えば、紀元後一世紀初頭から四世紀初頭までの約300年である。この時代の話となると、その対象地域はどうしても西日本に集中してしまう。悲しいかな、東日本は蚊帳の外にされるのが常である。しかし、当然のことながら、その時代の日本列島は西日本だけで動いていたわけではなく、東日本は眠っていたわけではない。邪馬台国の時代は、汎列島的な規模での動乱期であった。その当時、列島の東西は連動していた。今も昔も、西日本と東日本とは日本の両翼であり、両者が相俟って歴史を紡いできたし、今後もそうあり続ける。
つまり、邪馬台国の問題を考える上で、東西交流という視点は重要であるということだ。「そんなこと言われなくても分かっている」。邪馬台国畿内(大和)説に立つ学者はこう返してくるであろう。なるほど畿内説は東西のことを視野に入れている。というのも、この説では邪馬台国は大和であり、それと対立する狗奴国は東海地方とされるからだ。近畿地方と東海地方とは政治的軍事的に敵対関係にあった。そういう意味で、東西は交流していた。これが畿内説の基本的な考えである。
私の考えはそれとは違う。それは拙著〔注1〕で説いた。一言で言うと、「倭国」と狗奴国との争いは東西対立ではなくて南北対立である。それが、私の呼ぶところの「淀川・関ヶ原ライン」と「大和川・青山峠ライン」という対抗軸である。今も昔も近畿地方には淀川水系と大和川水系との二つがある。邪馬台国畿内説は、両者を同じ畿内として十把一絡げにする。二つの水系を邪馬台国のテリトリーとしてひとまとめにしてしまう。しかし、邪馬台国の時代に関して言えば、そうした扱いは根本的に誤りである。その発想こそが邪馬台国畿内説最大の迷妄である。そう私は考える。
今日、大阪から名古屋に在来線で行くには二つの路線がある。
一つはJR東海道本線の上りであり、大阪、京都、米原、大垣、名古屋という順路である。これは、大阪平野から淀川沿いに進み、琵琶湖を横目に、関ヶ原を通って濃尾平野に入る道のりである。このJRルートが、淀川・関ヶ原ラインである。
もう一つは近鉄大阪線で大阪上本町、河内国分、桜井、名張、伊勢中川に至り、そこで近鉄名古屋線に乗り換えて、津、近鉄四日市、桑名、近鉄名古屋の順路となる。これは、大阪平野から大和川に重なるように奈良盆地に入り、更に東進して青山峠付近から伊勢へ抜け、そこから伊勢湾沿いに北上して濃尾平野に入る道のりである。この近鉄ルートが、大和川・青山峠ラインである。
近畿地方と東海地方とを結ぶこの二つのラインは、古においても同じく交通路であった。弥生時代後期~庄内式期において日本列島の東西は交流していた。その主要な交流ルートは二つあったというのが私の考えである。
そして、三世紀の倭国と狗奴国との抗争は、この二つのラインのせめぎ合いであった。それを南北対立と言ったのはそういう意味である。北の淀川・関ヶ原ラインが倭国の勢力圏であり、その中心は吉備王権である。南の大和川・青山峠ラインが狗奴国の勢力圏であり、その中心は大和政権である。以上が私の説である〔注1〕。
本シリーズで取り上げるのは、専ら淀川・関ヶ原ラインである。これは日本列島の東西を結ぶ物流の幹線であった。そのことを示す格好の材料がある。それがガラス製品である。ガラス素材は古墳時代終末期(七世紀)に至るまで国産されなかった。弥生時代および古墳時代前期のガラス製品は舶来品であり、おそらく北部九州で荷揚げされ、西から東へ運ばれた。つまりそれは、古代における東西交流を知るのにうってつけの材料なのである。この点が、銅鐸や銅鏡などとの大きな違いである。銅鐸は国産品であり、銅鏡の一部は国産品(仿製鏡)である。従ってそれらは必ずしも北部九州から東国まで運搬されたわけではない。それらは必ずしも東西交流に依るわけではない。
岐阜県美濃市の美濃観音寺山古墳は、前方後円墳集成編年1期、すなわち250年代の古墳である。ここから2点の翡翠勾玉、3点の水晶小玉、18点のガラス小玉が出土している。
長野県松本市の弘法山古墳は、庄内3式~布留0式期の古墳である。ここから738個のガラス小玉が出土している。
千葉県市原市に神門5号墳、神門4号墳、神門3号墳がある。5号墳は庄内3式併行期、4号墳は庄内3式~布留0式古相併行期、3号墳は布留0式古相併行期である。5号墳からは6個のガラス小玉が出土し、4号墳からは31個の管玉と394個のガラス小玉が出土し、3号墳からは10個の管玉と103個のガラス小玉が出土している。
以上のように、庄内3式併行期~布留0式古相併行期(240~260年)にガラス小玉は東日本に搬入されていた。それでは、それはどのルートで運ばれたのだろうか?
京都府城陽市の芝ヶ原古墳は、庄内式期新段階~布留式期最古段階の古墳である。ここから、8点の翡翠製勾玉、187点の碧玉製および緑色凝灰岩製の管玉、そして1264点のガラス小玉が出土している。
大阪府高槻市の安満宮山古墳は、布留0式古相併行期の古墳である。ここから、1641点のガラス小玉が出土している。
芝ヶ原古墳と安満宮山古墳はどちらも淀川水系の古墳である。つまり、庄内3式併行期~布留0式古相併行期に、ガラス小玉は淀川水系の有力者にもたらされていた。なお、この二つの古墳については、次回以降に個別に触れる予定である。
ところが、同じ近畿地方でも、奈良盆地となると話が違ってくる。弥生時代終末期から古墳時代初頭の墳墓・古墳のうちで、埋葬施設が調査されたのは、ホケノ山古墳、中山大塚古墳、上牧久渡3号墳である。これらから、ガラス小玉はおろかそもそも玉類が出土していない。布留0式期新相の黒塚古墳からも玉類は出ていない。
大和川水系に属する奈良盆地で、玉類を出した最古の古墳は、桜井市の桜井茶臼山古墳と天理市の下池山古墳である。前者からは硬玉勾玉、碧玉管玉、ガラス管玉、ガラス玉が、後者からはヒスイ勾玉、碧玉管玉、ガラス小玉が出土した。これらは布留1式期の古墳であり、従って270年以降である。大和川水系では、240~260年にガラス製品が副葬された古墳がまだ見つかっていない。
なお、奈良県でも盆地の外に目を向けると、宇陀市に見田大沢墳墓群がある。その2号墳は布留1式期、4号墳は布留0式期古相の墳墓である。2号墳からは、1点の琥珀勾玉、7点の緑色凝灰岩製管玉、2点のガラス小玉が出土した。4号墳から、1点の翡翠製勾玉、7点の緑色凝灰岩製の管玉が出土した。この墳墓群は、大和川水系ではなくて、淀川水系に属する。
以上のことから、ガラス小玉は三世紀前半に淀川・関ヶ原ラインを介して東日本へ運ばれたと推定される。一方、その段階では大和川・青山峠ラインはガラス製品の運送に関わっていなかったと思われる。このことは、淀川水系と大和川水系とを一緒くたにして邪馬台国を論ずることが、いかに大きな見当違いであるかの証左である。
つづく
〔注1〕若井正一 2019『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権』一粒書房
令和3年3月28日投稿
以上、2021年3月28日投稿記事
2025年8月11日投稿