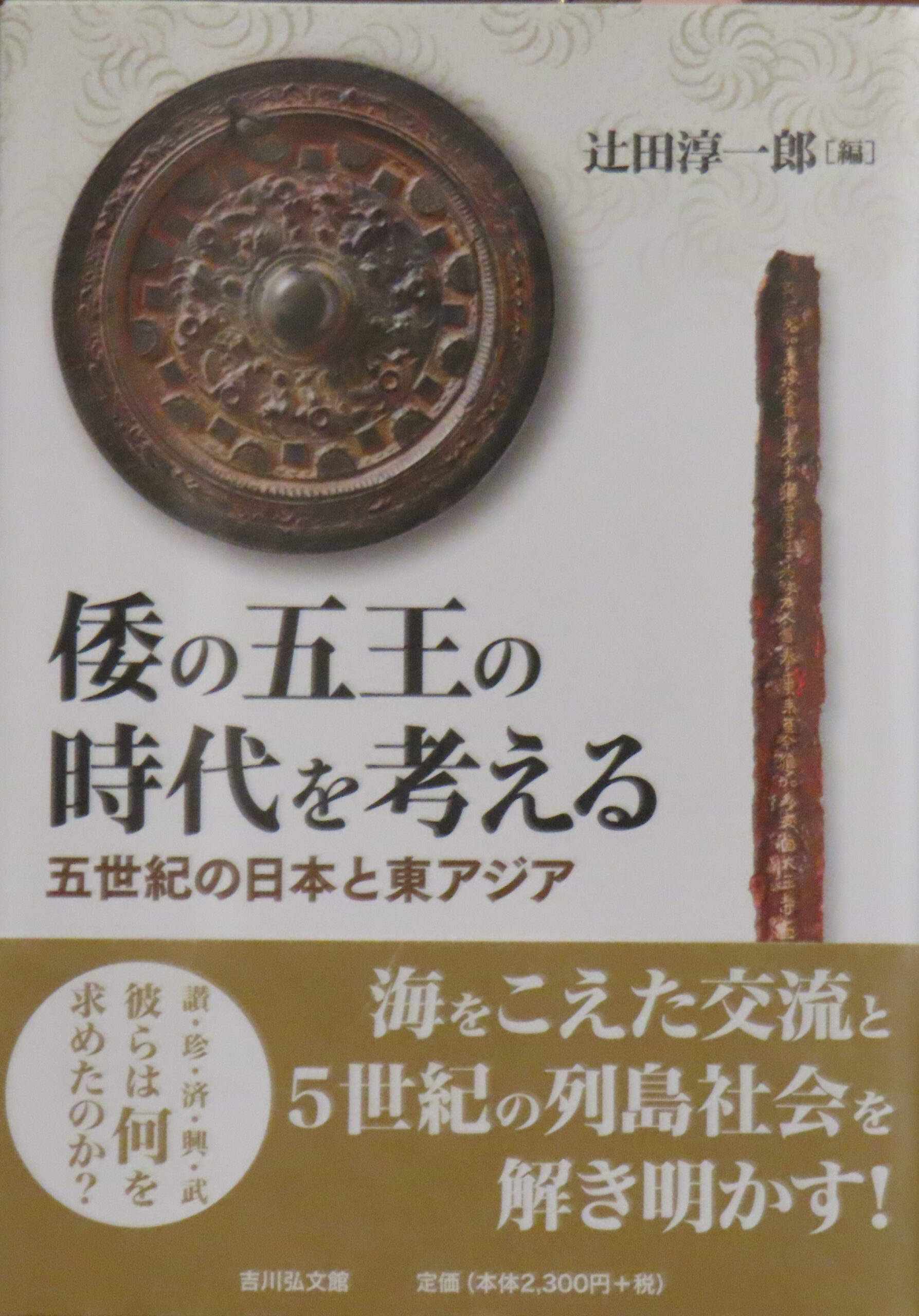<第一節> 「倭の五王」研究の古代史学界の現状
中国の正史『宋書』倭国伝によれば、倭の「讃」(さん)、「珍」(ちん)、「済」(せい)、「興」(こう)、「武」(ぶ)が次々と中国の南朝に遣使しました。これが「倭の五王」です。
今日の古代史アカデミーはこのテーマを大変に重視しています。それを受けて、高等学校日本史教科書ではその本文で取り上げられています。とともに、「倭の五王」をタイトルに掲げる書籍がいくつも出版されています〔注1〕。昨年に上梓された『倭の五王の時代を考える』(アイキャッチ画像)もまたその一つです〔注1④〕。
南朝・宋に遣使したのが大和政権であることは間違いありません。そこで、各々の倭王が『古事記』『日本書紀』(以下、『記』『紀』と略す)のどの天皇に当たるのかが長年にわたって議論されてきました。しかしこの論争はいまだ決着していません。それは、『宋書』倭国伝、『記』『紀』、暦年代の三つが整合性に欠けるからです。
そのため、倭の五王を論じながら、『記』『紀』の天皇への言及を避ける論文・書籍は決して少なくありません。例えば、上述の『倭の五王の時代を考える』には二名の古代史専門家が寄稿していますが、そのうちの一人である田中史生氏の論文がその典型です〔注2〕。君子危うきに近寄らず、というわけです。
倭の五王を語るのに、なぜ古代史専門家は倭の史書を脇に置くことに疑問を感じないのでしょうか?その理由は、河内春人氏の次の言葉に露わになっています。
曰く、「五世紀の倭国史について考えるとき、『宋書』倭国伝と記・紀のいずれに重点を置くべきかはいうまでもない。まずは『宋書』倭国伝を中心に据えるべきであり、記・紀はその補助史料として位置づけられるべきである。もちろんこれまでもそうした研究はあり、大きな成果をもたらした。ただし、現代日本人の意識の根底にはまだ記・紀を主軸とする考えがある。本書は、倭の五王を、ひいては五世紀の倭国を理解するために、記・紀以外からどのような歴史をうかがえるのかを試みる。そこからは王権、国の組織のあり方、文化レベルなど記・紀が作り上げたイメージとは異なる五世紀の東アジアの歴史が眼前に姿を現すことになる。本書によって、日本の立場だけで日本史を考える危うさについて気付くきっかけになればと思う」〔注1③、「はじめに」〕〔太字は引用者による〕と。
上述の『倭の五王の時代を考える』の執筆者の一人である古代史家の古市晃氏もまた同様な考えを表します。曰く、「西暦五世紀にあたる倭の五王の時代について、列島社会の様相を明らかにする文献史料はきわめて乏しい。かつて盛んに用いられた『古事記』『日本書紀』(以下、記紀)は、これまでの長い研究の積み重ねによって、天皇の統治の正当性を主張するための歴史観に基づく多くの造作が含まれていることが明らかにされている」〔注3〕〔太字は引用者による〕と。
ちなみに、古市氏の歴史観によれば、「記紀が記す天皇で実在が確実視されているのは、第一五代応神天皇、または第一六代仁徳天皇からであって、それ以前の天皇は後世の造作にすぎない。記紀などに記されている陵墓の所在地と、巨大前方後円墳の集中する地が一致することや、陵墓に比定される古墳の年代観と歴代天皇の治世が近似するという見解から、第一〇代崇神天皇以降の天皇が実在したとする主張もあるが、そうした主張は文献史学や考古学の固有の方法論を無視したもので、学術的には何の意義も有さない」〔注4、頁12〕〔太字は引用者による〕とのことです。
「記紀などに記されている陵墓の所在地と、巨大前方後円墳の集中する地が一致することや、陵墓に比定される古墳の年代観と歴代天皇の治世が近似する」ならば、『記』『紀』の系譜や記事の信憑性が俄然高まると普通は思ってしまいます。ところが、そういう思考は「文献史学や考古学の固有の方法論を無視した」ものであり、もってのほかなのだそうです。
さしずめ私がこれまで行ってきた研究などは、古市氏の見解からすれば、「学術的には何の意義も有さない」最たるものと言えましょう。
要するに、中国の史書を金科玉条のごとく扱う一方で、『記』『紀』は信憑性に乏しい史料であると見下すのが、我が国の古代史学者の習いなのです。
倭の五王を論ずるに当たって、彼ら古代史専門家には共通の前提があります。それは次の二つです。
(1)倭の五王の各々は互いに別の人物である。
讃・珍・済・興・武の五名の王は、応神天皇(第十五代)、仁徳天皇(第十六代)、履中天皇(第十七代)、反正天皇(第十八代)、允恭天皇(第十九代)、安康天皇(第二十代)、雄略天皇(第二十一代)の七名の天皇のうちの五名と、一対一に対応するという前提です。
(2)倭の五王の系譜関係は正確である。
『宋書』倭国伝によると、「讃」の弟が「珍」であり、「済」の子が「興」であり、「興」の弟が「武」です。この関係こそが真実であるという前提です。ただし、「讃」「珍」と「済」「興」「武」との関係は記されていません。
この前提から、『宋書』倭国伝と『記』『紀』との系譜の一致は絶対的なものではないという考えが派生します。どうせ『記』『紀』の系譜はあてにならないものだから、一致しなくても気にする必要はない、というわけです。
さて、前置きはここまでとして、倭の五王がどの天皇に当たるのかを考えてみましょう。
『記』『紀』によれば、応神天皇(第十五代)の子が仁徳天皇(第十六代)であり、仁徳天皇の三人の子が履中天皇(第十七代)、反正天皇(第十八代)、允恭天皇(第十九代)であり、允恭天皇の二人の子が安康天皇(第二十代)、雄略天皇(第二十一代)です。
そこで、『宋書』倭国伝と『記』『紀』との系譜の整合性だけに拘るならば、「倭王武が雄略=稲荷山古墳出土鉄剣銘にみえるワカタケル大王にあたることを定点として、興を安康、済を允恭とする点は諸説ほぼ一致している。讃と珍については諸説あるが、記紀の皇統譜との対応関係を重視するならば、讃を履中、珍を反正とするのが妥当であろう」〔注3〕となります。
かくの如く、讃=履中天皇、珍=反正天皇、済=允恭天皇、興=安康天皇、武=雄略天皇に比定すれば全て丸く収まるわけです。
ところが実際には、この比定で一件落着しているわけではありません。
古代史学界では、「これまでの代表的な説を挙げれば、讃を第16代仁徳天皇、珍を第18代反正天皇、済を第19代允恭天皇、興を第20代安康天皇、武を第21代雄略天皇とする。讃・珍については他にも説があるが、済・興・武についてはほぼ確定的に考えられている」〔注1③、「はじめに」〕というのが現況なのです〔注5〕。
これを受けて、今日の代表的な高校日本史教科書である『詳説 日本史 日本史探究』(山川出版社 2023年発行)では、「『宋書』倭国伝に記されている倭の五王のうち、済とその子である興と武については『古事記』『日本書紀』にみられる允恭とその子の安康・雄略の各天皇に当てることにほとんど異論はないが、讃には応神・仁徳・履中天皇を当てる諸説があり、珍についても仁徳・反正天皇を当てる2説がある」(頁27)と注記されています。
それは何故なのでしょうか?なぜ讃と珍は定まらないのでしょうか?
これに関する古代史専門家の説明は総じて要領を得ないものであり、説得力十分なものを寡聞にして知りません。
そこで、ここでは私見で説明します。
讃を履中天皇に当てた場合の大きな問題は暦年代にあります。
『宋書』倭国伝によると、讃は西暦421年と425年に遣使しました。もし讃が履中天皇(第十七代)であるならば、421年は履中天皇の御世であるわけです。とすると、その先代である仁徳天皇(第十六代)の崩御は遅くても五世紀初頭となり、そのまた先代である応神天皇(第十五代)の崩御は四世紀後半となります。
ところで、応神天皇の陵は誉田御廟山古墳(こんだごびょうやまこふん)に、仁徳天皇の陵は大仙陵古墳(だいせんりょうこふん)に治定されています。ここでは詳細を省きますが、この治定は妥当です。
誉田御廟山古墳(大阪府羽曳野市誉田)は、墳丘長425㍍の前方後円墳であり、古市古墳群の盟主です。これは我が国第二位の規模を有する超巨大古墳です。その年代は413年頃です〔注6、第一章・第四節〕〔注7、頁429〕。
大仙陵古墳(大阪府堺市堺区大仙町)は、墳丘長486㍍の前方後円墳であり、百舌鳥古墳群の盟主です。これは我が国第一位の規模を有する超巨大古墳です。その年代は430年頃です〔注8、頁189〕。
とすると、応神天皇の崩御は四世紀後半ではあり得ません。同様に、仁徳天皇の崩御は五世紀初頭ではあり得ません。もし421年が履中天皇の御代であるとすると、先代の仁徳天皇の葬送儀式がその時点では未だ済んでおらず、その約9年後になって漸く実施されたことになります。これはあり得ません。
つまり、倭王・讃は履中天皇ではないのです。421年と425年の倭王・讃は仁徳天皇です。
<第二節> 「倭の五王」についての私説
私は拙著で倭の五王を次のように比定しました〔注7、頁580~587〕。
すなわち、「讃」は仁徳天皇(第十六代)であり、「珍」は履中天皇(第十七代)ないしは反正天皇(第十八代)であり、「済」は允恭天皇(第十九代)であり、「興」と「武」は雄略天皇(第二十一代)です。
ちなみに、倭王・珍は438年に遣使しました。従って、珍は438年時点での天皇に当たります。珍は履中天皇か反正天皇かのどちらかですが、いずれとも確定できません。
このように比定した根拠の詳細は拙著〔注7、頁580~587〕に記しました。
先に、古代史専門家が共有する前提として、次の二つを指摘しました。第一に、倭の五王の各々は互いに別の人物であること、第二に、倭の五王の系譜関係は正確であることです。私は、倭の五王の比定に当たって、この二つを絶対条件としませんでした。その理由は拙著で述べました。
私説が定説と決定的に異なるのは、興と武とは同一人物であり、それを雄略天皇とする点です。興は定説では安康天皇ですが、私説では雄略天皇です。
本稿では、なぜ倭王・興が雄略天皇であるのかに絞って説明します。
『宋書』倭国伝によると、興は西暦462年に遣使しました。
つまり、倭王・興は誰かとは、462年時点での天皇は誰かということです。
そこで問題になるのが『日本書紀』の紀年です〔注6、第一章・第三節〕。
古の我が国では暦によって歴史を伝承していませんでした。そのため、初期天皇の御代の『日本書紀』紀年は実年代ではありません。それでは、どの段階からその年紀が信頼できるのでしょうか?この問題に突破口を開いたのは、小川清彦氏による『日本書紀』の暦日に関する研究です。小川氏は、安康天皇(第二十代)の段を境にして、その暦日が元嘉暦に変わることを見出しました。これは今日において定説となっています〔注9〕。このことから、まさにその頃から暦による年紀が始まったことが分かります。よって、『日本書紀』において、雄略天皇(第二十一代)段の紀年は実年代なのです〔注10〕。
以下で示す西暦は、内田正男(編著)『日本書紀暦日原典』〔新装版〕(雄山閣 1993年)によります。
雄略天皇は西暦456年11月に即位しました。雄略天皇元年は457年です。そして、雄略天皇二十三年八月に崩御しました。これは西暦479年八月です。この間が雄略天皇の治世です。
倭王・興が遣使したのが西暦462年です。倭王・武が遣使したのが478年です。どちらも雄略天皇の御代です。だから、興と武のどちらも雄略天皇なのです。
先述したように、高等学校では、「『宋書』倭国伝に記されている倭の五王のうち、済とその子である興と武については『古事記』『日本書紀』にみられる允恭とその子の安康・雄略の各天皇に当てることにほとんど異論はない」と教えられています。しかし、この説明は「興」について言えば誤りです。
<第三節> 『日本書紀』雄略天皇段の暦年代
実を言うと、『日本書紀』雄略天皇段の紀年が正確であることには決定的な証拠があります。
それは雄略天皇五年の条です。
・雄略天皇五年四月条:百済の蓋鹵王(がいろおう)が弟である「軍君」(こにきし)に「日本へ行って天皇に仕えよ」と命じました。それに対して軍君は、王妃を自分に降嫁して欲しいと要望しました。そこで蓋鹵王は、自らの子を身籠もった王妃を弟と結婚させました。その時すでに王妃は臨月を迎えていました。軍君とその妊婦は蓋鹵王に暇乞いをし、日本に向かいました。
・同五年六月条:蓋鹵王の子を身籠もった妊婦が「筑紫の各羅島」(つくしのかからのしま)にて出産しました〔注11〕。そこでこの子を「島君」と名付けました。軍君はこの母子を同じ船に乗せて百済に帰国させました。この子が後の百済の武寧王(ぶねいおう)です。
・同五年七月条:軍君が大和に入りました。
・同五年七月条・割注:『百済新撰』に「辛丑の年に、蓋鹵王は王弟の琨支君(こにききし)を遣わして、大倭に参向させて天皇に仕えさせ、兄王の好誼を修めた」とあります。
上記のうち五年七月条・割注にある『百済新撰』とは、百済の史書であり、いわゆる百済三書のうちの一つです。百済三書は『日本書紀』が引く逸文だけが残り、他はすべて失われています。
蓋鹵王の在任時期(西暦455年~475年)中の「辛丑の年」は西暦461年に当たります。つまり、『日本書紀』の引用によれば、西暦461年に蓋鹵王が王弟を大和朝廷に派遣したと『百済新撰』に記されていたわけです。
さて、『日本書紀』の紀年では、雄略天皇五年は西暦461年に当たります。
つまり、『日本書紀』本文にしろ、『日本書紀』が引く『百済新撰』にしろ、一致して、461年に百済の蓋鹵王が弟を大和朝廷に派遣したと記しているわけです。そして、この年に武寧王が生まれたわけです。
ところが、この話は信用されていませんでした。「韓国の文献史料には記載がないことから、これまでは日本側史料の恣意的な記述であるとみられていた」〔注12、引用部の執筆は赤司善彦氏〕のです。要するに、『日本書紀』の作り話であると思われていたのです。
ところが、です。1971年に考古学上の大発見がありました。
大韓民国忠清南道公州市の宋山里古墳群から、武寧王とその王妃の墓が未盗掘の状態で発見されたことです。
そこには墓誌があり、「寧東大将軍百済斯麻王、年六十二歳、癸卯年五月丙戌朔七日壬辰崩到」と記されていました〔注13〕〔注14、頁165・頭注〕。
現代語訳すると、寧東大将軍である百済の斯麻王は、年六十二歳にして、癸卯年五月七日に亡くなった、となります〔注13〕。
この墓誌中に「斯麻王」とあります。『日本書紀』武烈天皇四年「是歳」条によれば、斯麻王は武寧王の諱(いみな)です。諱とは生前の本名のことです。つまり、墓誌中の「斯麻王」とは武寧王のことです。
墓誌中の「癸卯年」とは西暦523年に当たります。すなわち、百済の武寧王は、523年に62歳で亡くなったことが、この墓誌により判明したわけです。
ということは、逆算すると、武寧王は西暦461年に生まれたことになります。これは雄略天皇五年条の暦年代と一致します。
先述したように、武寧王の諱が斯麻王であることは、武烈天皇四年「是歳」条に依ります。そこに、「島王立つ。これが武寧王である」とあります。これは武寧王の即位記事です。武烈天皇四年とは西暦502年です。これが武寧王の即位年です。
この記事には割注があり、『百済新撰』からの引用として、「武寧王が立つ。諱は斯麻王という」とあります。それに続けて、「琨支が倭に参向した時に、筑紫島に到着して斯麻王を生んだ。そこで島から送還した。都に到着しないで島で生まれた。そのため、名付けたのである。今、各羅の海中に主島がある。王が産まれた島である。そこで、百済の人はその島を主島と名付けた」とあります〔注11〕。
これ(武烈天皇四年「是歳」条の記事)は、雄略天皇五年六月条と同内容ですが、この記事の独自性は、武寧王の諱が斯麻王であり、その由来が筑紫の島にあることを教えていることです。つまり、斯麻王とは「島王」であり、その読みは「しま王」なのです。このことは、武寧王が「筑紫の各羅島」で産まれたという雄略天皇五年六月条の記事の真実性を補強します。
以上見てきたように、武寧王の墓誌は次の二つのことを明らかにしました。
第一に、この王の諱が斯麻王であることです。
このことは、武烈天皇四年「是歳」条と相まって、雄略天皇五年六月条の記事が史実であることを裏付けます。
「韓国の文献史料には記載がないことから、これまでは日本側史料の恣意的な記述であるとみられていた」〔注12〕という従来の認識は誤りだったのです。
第二に、この王が生まれたのは461年であることです。これは雄略天皇五年の暦年代と一致します。
このことは、『日本書紀』雄略天皇段の年紀が正確であることを示します。先述したように、これは当時の大和朝廷が導入した元嘉暦に基づくものです。専門家が説くように、「五世紀後半の雄略朝ごろから、中国の暦日に基づく朝廷の記録が作られ始め、それは元嘉暦に依拠したものであった」〔注10〕のです。
以上より、461年が雄略天皇の御世であることが明白となりました。
ここで話を倭の五王に戻しましょう。
先述したように、倭王・興が遣使したのが462年です。ということは最早明らかです。倭王・興は雄略天皇(第二十一代)なのです。興は安康天皇(第二十代)ではありえません。
『日本書紀』雄略天皇六年四月条に、「呉国が使者を遣わして朝貢した」という記事があります。雄略天皇六年四月は462年です。「呉国」とは中国の南朝・宋のことです。私は、この記事は462年の倭王・興による遣使に対する答礼使の来日のことであると考えています〔注7、頁584〕。
武寧王の墓誌が発見されたのは1971年のことです。今から五十年以上も前のことです。ところが、不可解なことに、古代史専門家は倭の五王を論ずるに当たってこの墓誌に言及しません。少なくとも私は寡聞にして知りません。それは何故なのでしょうか?
案ずるに、『宋書』倭国伝の一語一句を無謬のものと信じる彼らにとって、この墓誌は不都合な真実だからです。
『宋書』倭国伝に、「興死す、弟の武立つ」とあります。倭王・武が雄略天皇(第二十一代)であることは確かです。『記』『紀』によると、雄略天皇は安康天皇(第二十代)の弟であり、かつ、その後継天皇です。とすると、彼らにとって、興が安康天皇(第二十代)であることは必然なのです。
『宋書』倭国伝が記す倭の五王は互いに別人であり(なぜなら名前を異にするから)、かつ、そこに記される系譜は正確であることを絶対条件とする彼らにとって、倭王・興が雄略天皇であることを示すこの墓誌は受け容れ難いわけです。
もしかしたら彼らは次のように考えているのかもしれません。
武寧王の墓誌の内容はなるほど史実である。武寧王の諱が斯麻王であり、その誕生年が461年であるのは確かである。しかし、だからといって、それが雄略天皇の御代のことである保証はどこにあるのか?それは、『日本書紀』だけが言っていることではないか。『日本書紀』の編者は、武寧王の誕生に関わることを、雄略天皇の御代のことに捏ち上げたに違いない、と。
もし、このような思考が正しいならば、雄略天皇の実在そのものが怪しくなります。「記紀が記す天皇で実在が確実視されているのは、第一五代応神天皇、または第一六代仁徳天皇からであって、それ以前の天皇は後世の造作にすぎない」〔注4、頁12〕どころの話ではありません。『日本書紀』という史書そのものが、偽書・偽作の類いということになります。
古代史の専門家と称する彼らが、そんな代物に頼っていてよいのでしょうか?「史料批判」なる魔法によって『古事記』『日本書紀』の記事をさしたる根拠を示すことなく作り話と決めつけ、その一方で、『記』『紀』から都合よく記事を切り取って自説の根拠とする。こんな欺瞞はもう止めるべきではないでしょうか。
むしろ、いっそのこと、「倭の五王を、ひいては五世紀の倭国を理解するために、記・紀以外からどのような歴史をうかがえるのかを試みる」〔注1③、「はじめに」〕ことに徹するべきではないでしょうか。それが可能であればの話ですが。
注:
〔注1〕私の手元にあるだけでも、次のものがあります。①坂元義種 1981『倭の五王 空白の五世紀』教育社、②森公章 2010『日本史リブレット人002 倭の五王 5世紀の東アジアと倭王群像』山川出版社、③河内春人 2018『倭の五王 王位継承と五世紀の東アジア』(中公新書)中央公論新社、④辻田淳一郎(編) 2025『倭の五王の時代を考える 五世紀の日本と東アジア』吉川弘文館
〔注2〕田中史生 2025「倭の五王の南朝遣使とその背景」辻田淳一郎(編)『倭の五王の時代を考える 五世紀の日本と東アジア』吉川弘文館
〔注3〕古市晃 2025「倭の五王の時代の王宮と社会」辻田淳一郎(編)『倭の五王の時代を考える 五世紀の日本と東アジア』吉川弘文館
〔注4〕古市晃 2021『倭国 古代国家への道』(講談社現代新書)講談社
〔注5〕一つ付言すると、河内春人氏はこの学会の定説を採っているわけではありません。というのも、河内氏は、「天皇系譜は五世紀以来、政治的変動や歴史書の編纂のなかで追加や削除が繰り返されてきたものである。それをふまえずに誰に当てはまるかを議論しても、それは実りある結論を生み出すことはない。倭の五王は、記・紀に拘泥せずにひとまずそれを切り離して五世紀の歴史を組み立ててみる作業が必要なのであり、本書はそのための露払いである」〔注1③、頁206〕という立場だからです。
要するに、『記』『紀』が記す五世紀の皇統譜は史実ではないので、『宋書』倭国伝の倭の五王が誰なのかを議論すること自体がナンセンスであるというのが河内氏の考えなのです。
〔注6〕若井正一 2019『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権 物部氏と卑弥呼と皇室の鏡を巡る物語』一粒書房
〔注7〕若井正一 2025『倭国の激動と任那の興亡 列島国家への軌跡』一粒書房
〔注8〕松木武彦 2025『古墳時代の歴史』(講談社現代新書)講談社
〔注9〕細井浩志 2018「日本書紀の暦日について 雄略紀を中心に」遠藤慶太ら四名(編)『日本書紀の誕生 編纂と受容の歴史』八木書店
〔注10〕東野治之 2006「七世紀以前の金石文」上原真人ら四名(編)『列島の古代史6 言語と文字』岩波書店
〔注11〕「筑紫の各羅島」とは、佐賀県唐津市の玄界灘に浮かぶ小島、加唐島(かからしま)(唐津市鎮西町加唐島)のこととする説があります。
〔注12〕赤司善彦ら七名 2014「加唐島武寧王伝説の調査について」『東風西声』九州国立博物館紀要 第9号:九州国立博物館
〔注13〕三上喜孝 2023「百済と倭」佐藤信(編)『古代史講義 【海外交流篇】』(ちくま新書)筑摩書房
〔注14〕小島憲之ら五名(校注・訳) 1996『新編日本古典文学全集3 日本書紀②』小学館
2026年1月6日 投稿