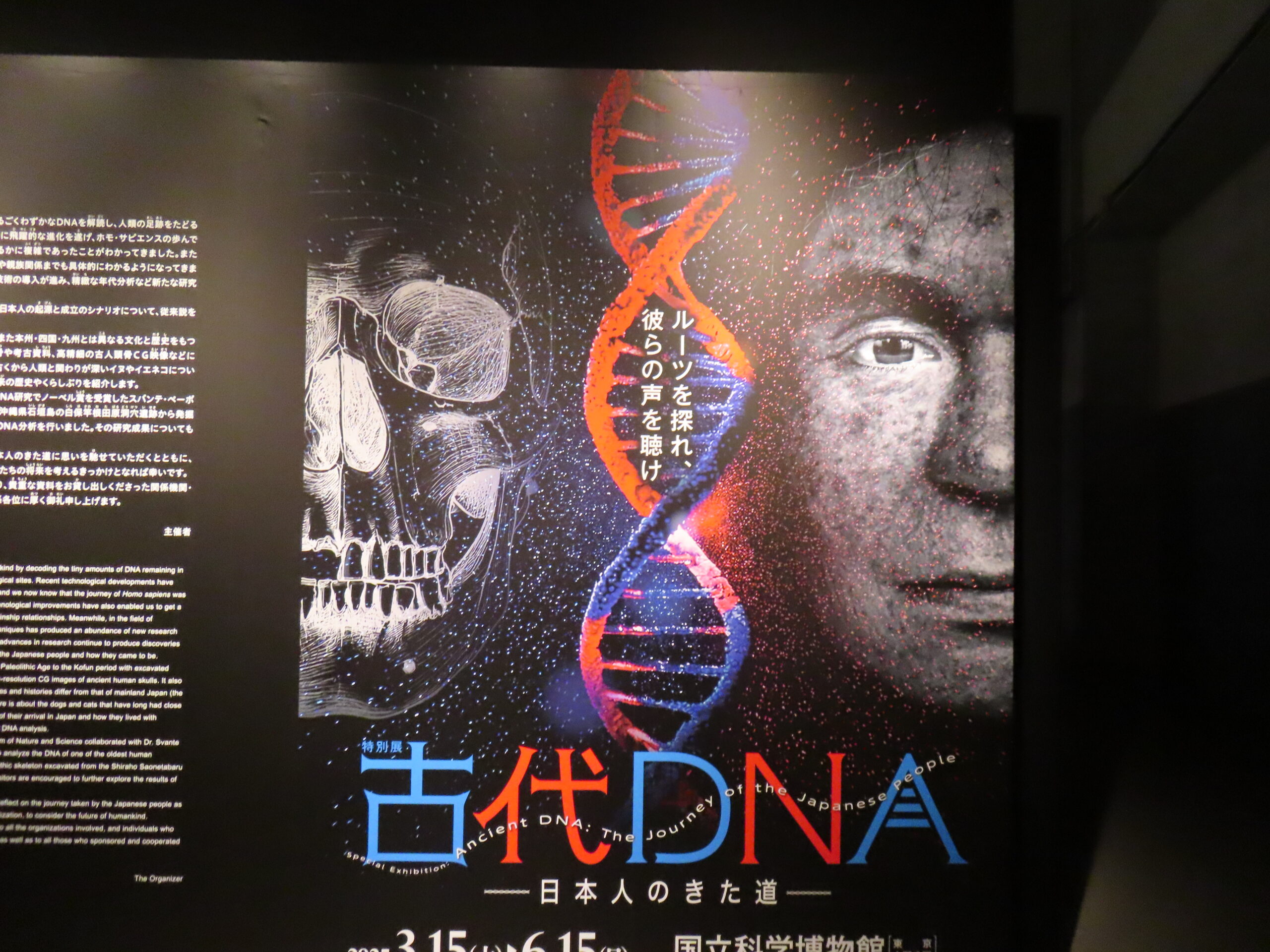以下は、2020年4月12日に投稿した記事です。
続・考古学者が邪馬台国畿内説から離れ始めた!?
「考古学者が邪馬台国畿内説から離れ始めた!?」の続きである。
邪馬台国論争の今後の方向性について私見を述べたい。
邪馬台国の所在地を巡って、九州説と畿内説とが長年に亘って対峙しているのは周知の事実である。近年、両者の論争は年代論を主戦場としてきた。古墳時代の始まり、すなわち箸墓古墳の築造は一体いつであったのか?九州説はそれを四世紀とし、畿内説はそれを三世紀中頃する。
これには次のような背景事情がある。卑弥呼〔アイキャッチ画像:大阪府立弥生文化博物館展示「卑弥呼」像〕が世を去ったのは248年頃である。古墳時代の主役は大和政権である。ここまでは誰も異論はない。九州説は、卑弥呼政権と大和政権とが別とする立場である。それに対して畿内説は、卑弥呼政権から大和政権へ繋がったとする立場である。そのため、九州説にとって、卑弥呼の時代と古墳時代とが離れていることが望ましい。一方、畿内説にとって、両者が連続していることが望ましい。
従来の考古学的手法だけでは袋小路に陥っていた。その閉塞状況に風穴を開けたのが、近年発展目覚ましい科学的年代測定法である。そのお陰で古代の年代を覆う霧は次第に薄らいできた。ことごとく畿内説に軍配が上がることによって。その流れに棹さす形で論争に決着を付けたのが、纏向遺跡から出土した桃核の年代測定結果である。
2010年に桜井市教育委員会は纏向遺跡第168次調査を行った。その対象区域は、それまでに検出されていた桜井市大字辻の大型建物群の南隣接地であった。この調査で、大型土坑(SK-3001)から2769点の桃核が出土した〔注1〕。共伴して出土した土器から、この桃核は庄内3式期新相のものと判明した。建物群を解体した時に執り行われた祭祀で供献されたものと推定されている〔注1〕。
桜井市教育委員会は、複数の専門機関に依頼して、桃核の炭素年代を測定することにした。庄内3式期新相、すなわち弥生時代終末期(庄内式期)の最終段階の暦年代を知るためである。それは全国的に大きな関心の的となった。弥生時代から古墳時代への移行期を巡る長年の年代論争に終止符を打つことが期待されたからである。
2018年に待ちに待った測定結果が二本の論文として発表された〔注2〕〔注3〕。二つの異なる専門機関が測定したものであるが、どちらも同様な年代を示した。日本産樹木の炭素14年代グラフ(JCal)に依れば、それは三世紀前半である。このことは、土器年代の庄内3式期が歴年代の三世紀前半に当たることを示している。これは、考古学者による近年の年代観に合致するものである。とともに、邪馬台国畿内説が想定する年代観を支持するものである。
古墳時代開始期の年代を巡る論争は、これにて勝負あった。私はそう考える。
それでは、邪馬台国論争は、これにて一件落着なのだろうか?私はそう思わない。
問題は、庄内式期の纏向遺跡の実態である。
邪馬台国畿内説がいうように、確かに庄内式期は三世紀前半、すなわち卑弥呼の時代である。それでは、畿内説がいうように、纏向遺跡が卑弥呼の都なのだろうか?近年、多くの考古学者はそうだと言う。
ところが、畿内を拠点とする考古学者でありながら、最近それに敢えて異を唱えたのが、坂靖である〔注4〕。「邪馬台国の時代、すなわち庄内式期においても、魏と交渉し、西日本一帯に影響力をおよぼしたような存在が、奈良盆地にはみあたらない。邪馬台国の所在地の第一候補とされる纏向遺跡の庄内式期の遺跡の規模は貧弱であり、魏との交渉にかかわる遺物がない。」〔注4、頁97〕という理由によってである。
その上で坂は、邪馬台国北部九州説に立つことを明らかにした〔注4、頁96〕。
私見では、今後の考古学上の邪馬台国論争は、坂が提起した問題を主要テーマとすべきであるし、またそうなるであろう。
ちなみに、邪馬台国吉備説に立つ私は、三世紀前半にあって纏向遺跡は全国的にみて先進的かつ特異な集落であると考える。ただしそれは、卑弥呼の都ではなくて、それと敵対関係にある狗奴国王の都である〔注5〕。
一つ付言したい。
「ヤマト王権とは何か」を問う件の著書〔注4〕において坂は、『日本書紀』について、「神武天皇が実在していたと考えることはできない」〔頁27〕とし、「神武天皇から崇神天皇に至る記述については、その編纂時点において暦年と天皇の血縁系譜の辻褄をあわせるために、明らかにそこに無理やり押し込んで記載されたものである」〔頁29〕と見る。初代・神武天皇から第九代・開化天皇までは実在しないと言うのだ。坂が戦後の正統的な古代史観に忠実に従う論者であることが分かる。
それに対して私は、『古事記』『日本書紀』にある皇統譜は史実であると考える。実は、私と坂とは同年齢であり(昭和36年生まれ)、おそらく同様な歴史教育を受けた者同士である。にもかかわらず、この懸隔はなぜ生じたのか?ある種の感慨を覚えざるを得ない。
ちなみに、最近、歴史研究会の機関誌の特集「日本書紀編纂千三百年」に拙文を寄稿した〔注6〕。そこにおいて、『日本書紀』が考古学と合致していることを指摘した。その拙文を本ブログに掲載する(それにリンクを張る)。
坂は言う。「蘇我氏が政権中枢にあった時代に、ヤマト王権は大王と氏族による支配構造を完成させている。それより前の時代については、文献と実態に乖離があることは、自明である。真実性のある文献資料は乏しく、その時代の遺跡や古墳と人物や人物の事績の記録を結びつけた歯切れのよい記述をすることは、歴史の真実からかえって遠のいてしまう。歴史の真実は、必ずやその実態の解明にある。ヤマト王権の実態は、古墳と地下に眠っている遺跡のなかに隠されている。」〔注4、頁269〕と。まさに考古学者の面目躍如といった感がある。
しかし、そうだろうか?寧ろこういう考えこそが、今行き詰まっているのではないのか。我が国の古文献を徒に無視し、中国文献に散在する短文と発掘により明かされた物証とを脈絡なく混ぜ合わせることで良しとする戦後の古代史こそが、今飽きられているのではないか。
「古墳と地下に眠っている遺跡」だけでは大和政権の実態を知ることはできない。「その時代の遺跡や古墳と人物や人物の事績の記録を結び」つけることこそが、「歴史の真実」に到達する唯一の道である。こう私は考える。
津田左右吉に始まる戦後の硬直した懐疑主義こそが、実は非合理的であり、独善的であり、教条主義的である。「文献と実態に乖離があることは、自明である」と頭から決めつける態度こそが偏向している。令和の新時代で求められているのは、戦前の皇国史観の復活ではなく、かといって戦後の唯物史観の継続でもなくて、それらを止揚した第三の史観の樹立である。こう私は信じる。
注:
〔注1〕橋本輝彦(編著) 2013『桜井市埋蔵文化財発掘調査報告書第40集 纏向遺跡発掘調査概要報告書―トリイノ前地区における発掘調査―』桜井市教育委員会
〔注2〕中村俊夫 2018「纏向遺跡出土のモモの核のAMS14C年代測定」『纏向学研究センター研究紀要 纏向学研究』第6号:桜井市纏向学研究センター
〔注3〕近藤玲 2018「纏向遺跡出土の桃核ほかと土器付着炭化物の炭素14年代法による年代測定について」『纏向学研究センター研究紀要 纏向学研究』第6号:桜井市纏向学研究センター
〔注4〕坂靖 2020『ヤマト王権の古代学 「おおやまと」の王から倭国の王へ』新泉社
〔注5〕若井正一 2019『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権 物部氏と卑弥呼と皇室の鏡を巡る物語』一粒書房
〔注6〕若井正一 2020「『日本書紀』と邪馬台国」吉成勇(編)『歴史研究』第680号(2020年4月号):歴研
2020年4月12日投稿
以上、2020年4月12日投稿記事
2025年9月20日 投稿