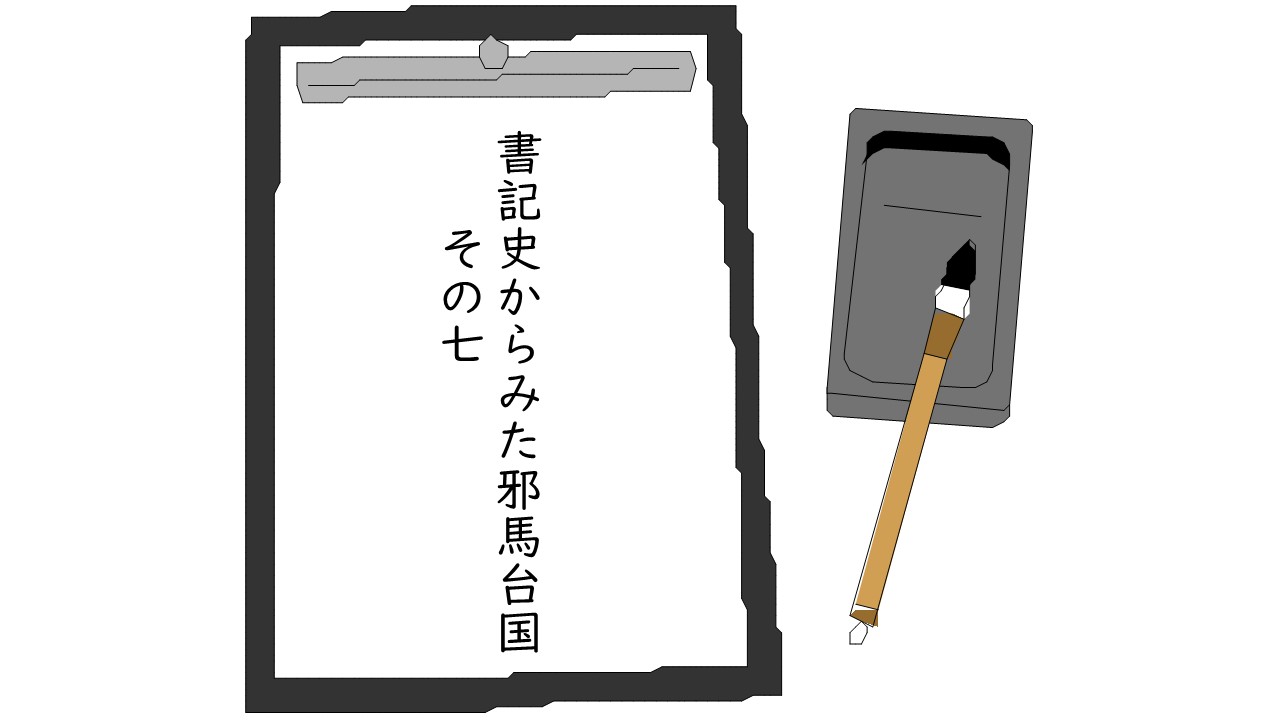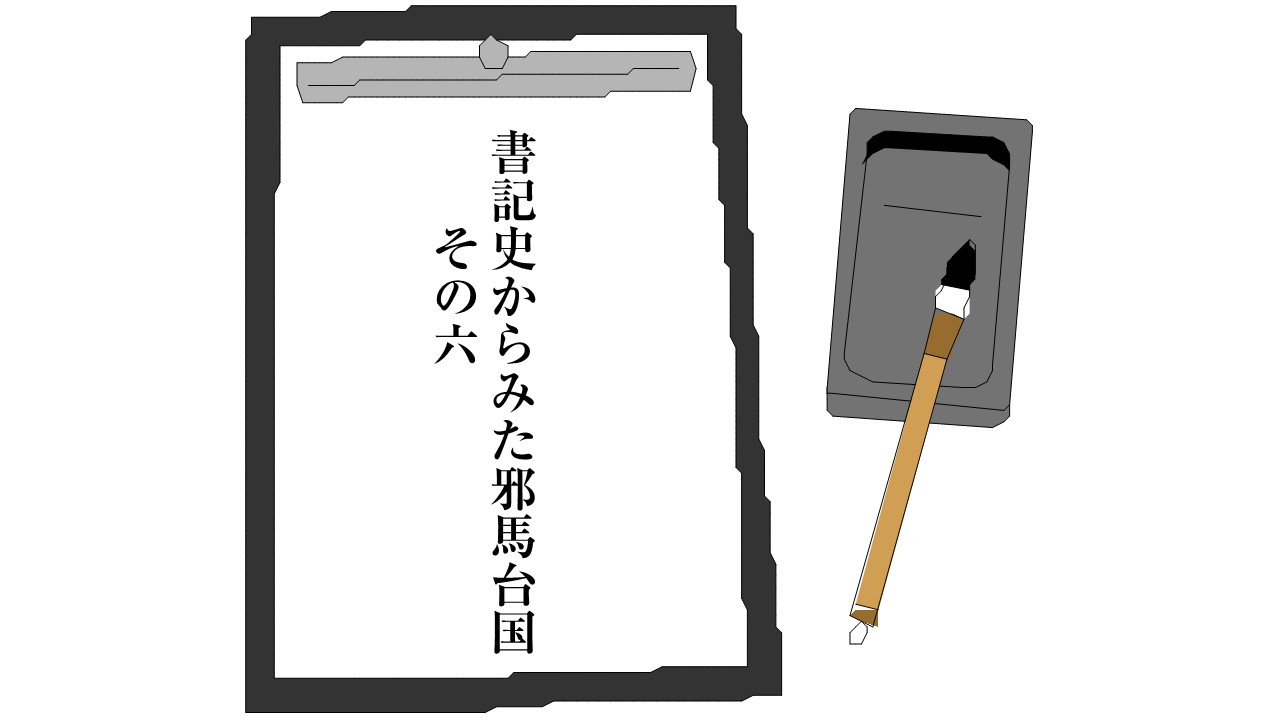以下は、2021年3月22日に投稿した記事です。
書記史からみた邪馬台国 その七
本稿は、「その一」、「その二」、「その三」、「その四」、「その五」、「その六」に続くものである。
ここまで「書記史からみた邪馬台国」と題して六本の記事をあげてきた。七本目の本稿を以てこのシリーズの結びとする。
これまで我が国の書記史のことを綴ってきたが、それと邪馬台国論との関わりには殆ど触れてこなかった。本稿ではそれを論じてシリーズを締めくくりたい。
ここ数年の考古学が明らかにしたのは、我が国の書記史は紀元前2世紀に遡ることだ。しかも、北部九州のみならず本州においても文書は作成されていた。三世紀に卑弥呼・台与が中国王朝との外交を執り行えたのは、長年に亘って積み重ねた書記のノウハウのお陰である。三世紀の邪馬台国が展開した文書外交は紀元前以来の伝統の延長線上にあった。ところが、中国史書によれば、倭国と中国との外交関係は266年を最後に途絶してしまった。再び倭国が外交の舞台に登場したのは413年である。この間、約150年、我が国と中国とは音信不通であった。いわゆる「空白の四世紀」である。
それでは、『古事記』『日本書紀』は我が国の書記の始まりをどのように伝えているのであろうか?
これについて『記』『紀』は概ね同じ内容の記事を掲載する。『紀』によれば、次のようになる。時代は応神天皇の御代である。百済が馬を献上し、それと共に一人の馬飼が渡来した。名を「阿直岐(あちき)」という。阿直岐は経典を読むことができた。そこで阿直岐を皇太子の教師とした。天皇が阿直岐に「より優れた学者はいるのか」と尋ねたところ、阿直岐は「王仁(わに)」の名を挙げた。そこで朝廷は百済に使者を派遣して王仁を招聘した。皇太子は王仁に師事して様々な典籍を学び、漢文に精通することができた。以上である。なお、『記』によれば、百済は、「和邇吉師(わにきし)」と共に『論語』十巻と『千字文』一巻を献上したという。
この話によれば、大和朝廷は百済から学者(王仁)を招くことで漢文を学び始めた。これが、『記』『紀』が記す書記史の始まりである。その御世は応神朝である。となると、それは四世紀末~五世紀初頭である。『論語』が我が国にもたらされたのはこの時である。それまで大和朝廷は史(文書を専門とする官人)を政権内部に抱えていなかった。
このことは、大和政権が弥生時代以来の書記の伝統と無縁であったことを意味する。三世紀の邪馬台国とは明らかに異なるのである。
書記史に見える断絶は、大和政権が中国史書の邪馬台国とは別であることを示す。邪馬台国大和説は成り立たないと私が考える理由の一つである。詳しくは拙著〔注1〕をご覧いただきたい。
了
〔注1〕若井正一 2019『邪馬台国吉備説からみた初期大和政権 物部氏と卑弥呼と皇室の鏡を巡る物語』一粒書房
以上、2021年3月22日投稿記事
2025年9月14日 投稿