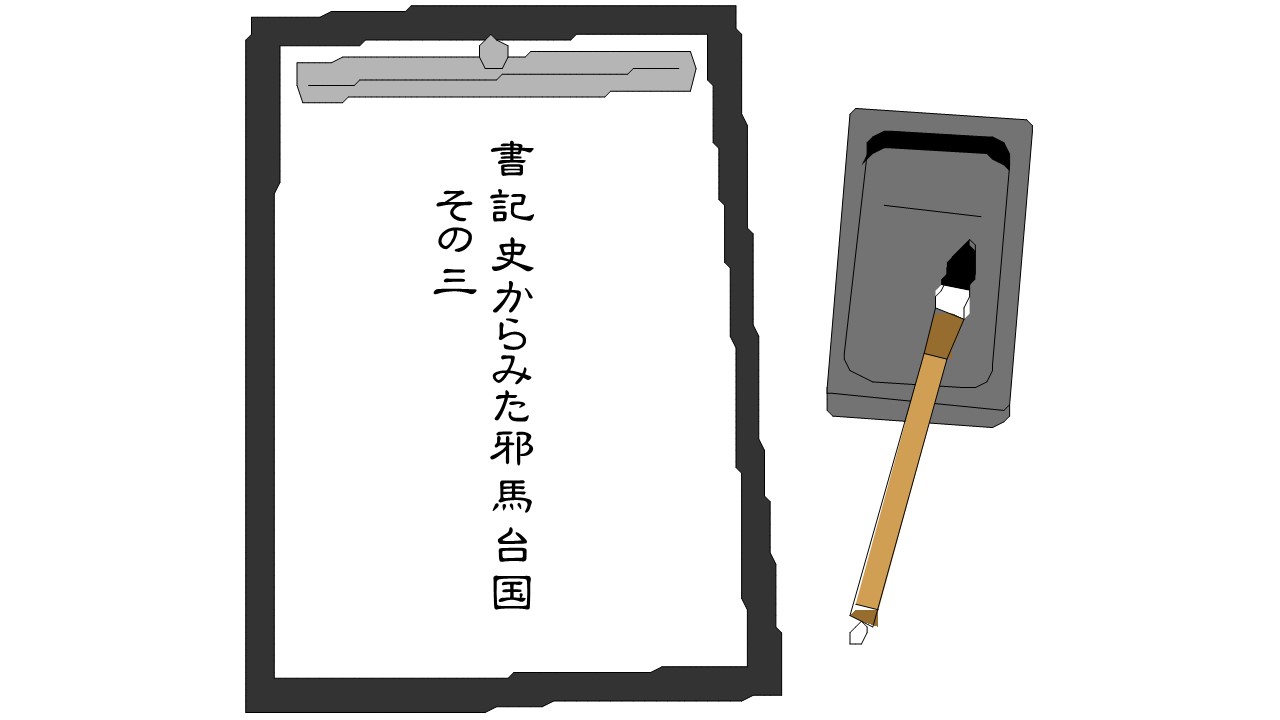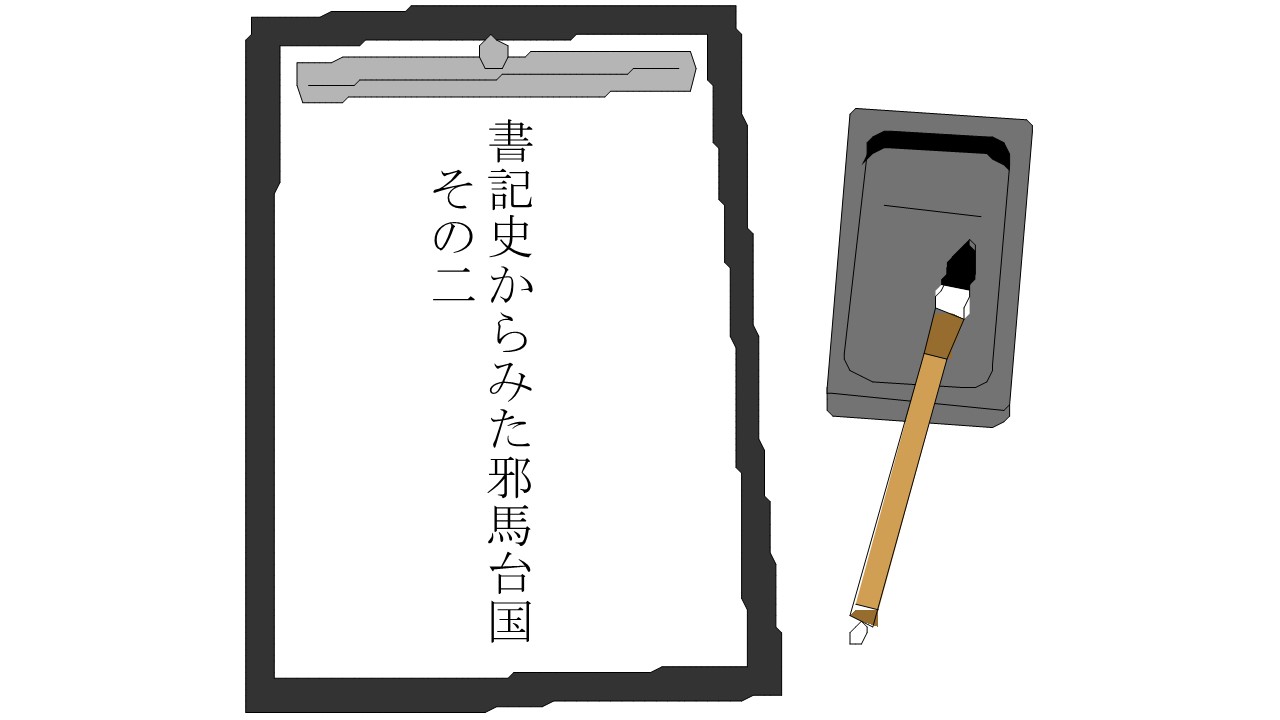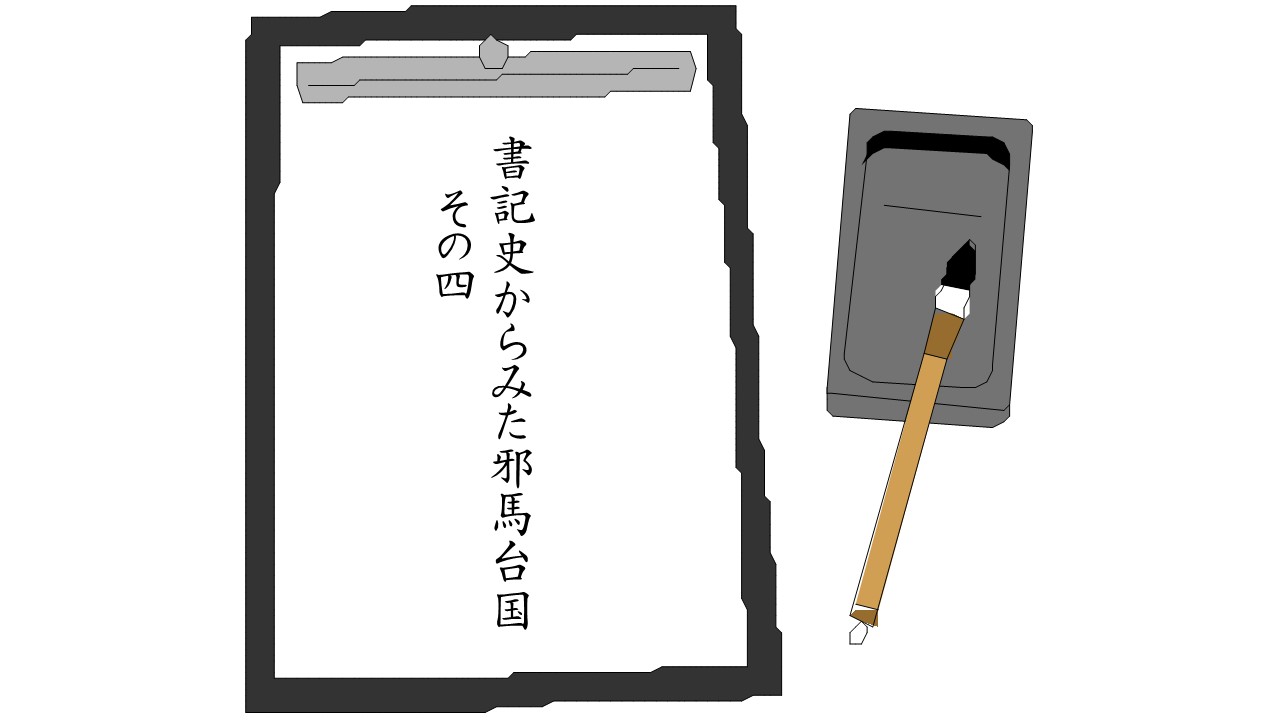以下は、2020年12月19日に投稿した記事です。
書記史からみた邪馬台国 その三
本稿は、「その一」、「その二」に続くものである。
魏志倭人伝によると、景初三年(239年)、魏王朝に初めて朝貢した卑弥呼は、「親魏倭王」に任じられ、「金印紫綬」を授与された上に、質量ともに破格の回賜品を賜った。その内の一つが、有名な「銅鏡百枚」である。卑弥呼の厚遇ぶりは誰の目にも明らかである。それはなぜなのだろうか?
有名な日本古代史家である仁藤敦史は曰く、「本来ならば東夷のとるにたらない国にすぎない倭国が、呉との対外関係上の問題から厚く遇されたことになる」〔注1、頁70〕と。
倭国は「本来ならば東夷のとるにたらない国にすぎない」が、魏は対立関係にあった呉への牽制のために、倭国を分不相応に厚遇した、というのだ。当時の中国は、魏、呉、蜀の三国時代であり、覇権を巡って魏は呉や蜀としのぎを削っていた。そうした政治情勢が倭国に有利に働いたというのだ。
しかし、本当に、倭国は「本来ならば東夷のとるにたらない国」にすぎなかったのだろうか?
古の我が国・我が祖先を低く評価するのは仁藤敦史に限らない。
『三国志』は、陳寿(ちんじゅ)という西晋の歴史家が撰述した、中国・三国時代の正史である。その中の魏書・東夷伝は、三世紀の東アジアを知るための根本史料である。そこでは民族ごとに地誌、風俗、社会などが記される。その民族とは、夫余(ふよ)、高句麗(こうくり)、東沃沮(とうよくそ)、挹婁(ゆうろう)、濊(わい)、韓、倭の七つである。このうち、倭人の条が、いわゆる魏志倭人伝である。
七つある条文のうちで最も多くの字数が費やされ(約2000字)、最も詳しく叙述されるのが倭人の条である。東夷の諸民族の内で、最も民度が高く、最もしっかりした統治機構を備えるのが倭人である。
このように、魏書・東夷伝は倭人を最も文明度が高い民族として描く。これは一体どういうことであろうか?
著名な中国古代史家である渡邉義浩は曰く、「本来的には高い文化を持っていたはずの朝鮮半島や中国の東北地方の諸民族の方が低い文化とされている原因は、東夷伝の執筆意図によるのである」〔注2、頁65〕と。その意図とは、「倭人伝は、陳寿の『三国志』が全体として持つ偏向を共有していた。司馬懿の功業を宣揚する、という目的のために、陳寿は、司馬懿の遼東平定に伴い来貢した倭国を、孫呉の脅威たるべき東南の大国として好意的に描いたのである」〔注2、頁142〕という。
魏書の東夷伝では、「本来的には高い文化を持っていたはずの朝鮮半島や中国の東北地方の諸民族の方」が、倭国より「低い文化とされている」。それは、倭国を「孫呉の脅威たるべき東南の大国」に仕立て上げるという陳寿の「偏向」による。そのため、そこで描かれる倭人・倭国は虚像である。東夷伝のうちの倭人は、高下駄を履かされている。そこで描かれる倭人は持ち上げられすぎている。こう渡邉は言うのだ。
しかし、本当に、朝鮮半島の諸民族の方が倭人よりも「本来的には高い文化を持っていた」のだろうか?
仁藤や渡邉によるこうした言説は象牙の塔において決して異端思想ではない。倭人は東夷の諸民族のなかで文化的に最も遅れた民族であるという認識は、アカデミズムの世界で広がっている。だが、史学者によるこうした認識は果たして妥当なのだろうか?それは、根拠のない固定観念に基づく思い込みではないのだろうか?
少なくとも言えるのは、彼らの主張は中国の史料や考古学上の事実と合わないことである。
弥生時代中期後半の紀元前一世紀中頃、伊都国の三雲南小路遺跡1号墓(福岡県糸島市三雲)や奴国の須玖岡本遺跡D地点墓(福岡県春日市岡本)では、多数の中国鏡(漢鏡2期および漢鏡3期)が副葬された。特筆すべきは、その中に大型鏡も含まれていることだ。
三雲南小路遺跡1号墓からは重圏彩画鏡一面(径27.3cm)、四乳羽状地文鏡一面(径19.3cm)の計二面。須玖岡本遺跡D地点墓からは草葉文鏡(復元径23cmあまり)三面。いずれも、漢鏡2期(紀元前二世紀後半の製作)の大型鏡である。
当時の中国では身分の違いによって保有する鏡の大きさが異なった。三雲南小路遺跡1号墓および須玖岡本遺跡D地点墓に副葬された計五面の大型鏡は、「中国では王侯クラスに贈与される」〔注3、頁22〕ものであった。これらの大型鏡は同時代の楽浪郡や朝鮮半島南部では出土していない〔注3、頁25〕。
つづく
〔注1〕仁藤敦史 2009『卑弥呼と台与』山川出版社
〔注2〕渡邉義浩 2012『魏志倭人伝の謎を解く』(中公新書)中央公論新社
〔注3〕岡村秀典 1999『三角縁神獣鏡の時代』吉川弘文館
以上、2020年12月19日投稿記事
2025年9月13日 投稿